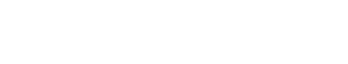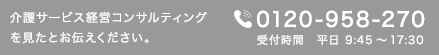訪問介護_軽度者の生活援助を地域支援事業へ移管か?
- カテゴリ:
- その他
コラムを開いてくださりありがとうございます。
介護福祉士の國原です。
在宅領域の担当をしています。
政権与党にかかわる総裁選が話題になっていますが、制度ビジネスである
介護事業において少なからず影響がある気がしています。
今回は軽度者外しと言われる訪問介護の要介護1・2の方の生活援助サービスについて詳しく書いていこうと思います。
目次
1.介護保険給付の抑制
2.介護保険における生活援助
3.要介護1・2の方の生活援助
4.総裁交代における影響は?
介護保険給付の抑制
介護給付費を抑制する制度改定は、財務省からの要望であり、常にその点においての指摘があります。議論に上がった内容は遅かれ早かれそちらの方向に動くが、いつ改定に反映されるかが我々の関心事となります。
介護保険における生活援助
介護保険における生活援助の必要性について議論があるのも事実です。
実際には自分でできるにも関わらず。安い自己負担でヘルパーが使えるのであれば使おうという、自立支援からかけ離れた使われ方をするヘルパーが一定の割合でいらっしゃいます。
そのことについて在宅訪問する事業者はご認識があるはずです。
一方で必要性が薄く感じる生活援助に関しても、本人の性格や生活環境、家族からの要望や認知症の有無などで総合的にケアマネがプランニングしていることもあり一概に自立支援の観点から問題があると言えないと私は考えています。
具体的には、認知症があり軽度の段階からヘルパーが自宅に入ることに慣れていないことで起る介護拒否などは事前に利用を開始することなどで緩和されることもあるためです。
要介護1・2の方の生活援助
事業者からよくお聴きするのは要介護1・2は軽度者か?ということです。
ご自宅でお過ごしの要介護者においてお体の元気な認知症の方の介護には大きな負担があると言われています。
果たして、要介護1・2の方の生活援助は削減すべきなのでしょうか?
私は生活援助にはいろいろな要素が内在しており、一概に論じることは大変に難しいと考えています。
総裁交代における影響は?
令和8年度は第10期の改定に向けて議論が活発していきます。
2割負担の利用者の拡大などは可能性としてあるが、すべての利用者に関わるケアプランの1割負担や、多くの事業者に影響の出る生活援助を市町村の地域支援事業へ移管する案は今回見送られるのではという意見もあります。
個人的には、スケジュールと世論から見送られるのでは?見送ってほしいという希望も含め議論の動向を見守っているところです。
自民党の新総裁はご主人の介護の経験があり、現在もされているということからどうか介護の事業者に手厚い待遇を進めてくれそうな姿勢を感じます。
私も含め制度ビジネスである介護事業者は与党のトップの交代に期待をしているのではないでしょうか?
この記事を書いたコンサルタント

國原 和真
医療・介護・福祉業界を専門とするコンサルティング会社にてHR戦略・M&A仲介・施設立ち上げなどの業務を担当。
事業会社にて、管理者として従事した経験もあり自身も介護福祉士資格を保有している。
コンサルティングと実務経験から経営者と現場、双方の立場を大切にした課題解決を信条としている。
船井総研に入社後は、介護・障害福祉事業を中心に支援を行っている。