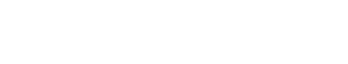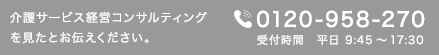第2回 介護の評価制度コラム ~正しい目的と目指すべき方向性 編~ 2/4
- カテゴリ:
- 人材採用・育成・評価 介護
第2回 介護の評価制度コラム
~正しい目的と目指すべき方向性編 2/4~
前回の『第1回 介護の評価制度コラム ~機能しない評価制度の特徴編1/4~』では、
人事評価制度が機能不全に陥るサインについてお伝えいたしました。
◆前回の内容はコチラ◆
今回は『評価制度の正しい目的と目指すべき方向性』についてです。
そもそも評価制度の主たる目的は、組織を導きたい方向へと導き、事業計画を実現することにあります。
これは経営者・本部の重要な仕事であり、現場の管理者にのみ委ねられるべきではありません。
よく耳にすることは、本来の目的抜きに
「”平等に・公正に・正確に”職員を評価するにはどうしたら良いですか?」という相談です。
これは「職員から不満が出ないようにしたい」という隠れた目的にすり替わっている証拠です。
本来の目的である「組織を導きたい方向へと導き、事業計画を実現する」を実現するためには、
評価制度の目指すべき方向性として二つの軸が存在します。
まず1つ目の軸は、
管理者の発掘・輩出(=人材育成)です。
事業所運営を担う管理者を育成し、事業計画の停滞や優秀な管理職の兼務過多による疲弊を防ぎます。
この一つ目の管理者輩出・人材育成については、評価制度の構築のご相談を頂く中でも、
ほぼ全経営者がゴールとして設定したいとおっしゃいます。
これだけでなく、ないがしろにされがちだが、管理者輩出と同じくらい大切2つ目の軸も存在します。
その2つ目の軸は、
課題職員の是正促進(=組織成長の阻害要因の縮小)です。
成長志向が強い方に対しては、
『人材育成』を目的にした制度設計で問題ないのですが、
下限を下回った言動をとる課題職員について、
きちんと是正を促すことがポジティブな育成と同様に重要になります。
組織が崩れたり、介護現場で多くの離職が発生する理由は、
人間関係であるケースが多いです。
「あの口調が強い人と一緒に働くのがつらい・・・」
「あの人だけいつも手伝ってくれない・・・」
「管理者が言ったことあの人だけ守ってないのに許されてる・・・」
「利用者のあの態度をとる方と同じ現場で働きたくない・・・」
こうしたことの是正を普段の管理者の指導に任せきりになってはいませんでしょうか?
管理者といえど、個人の力には限界があります。
このような課題職員に対して、時には強力な是正促進として
機能させることも評価制度では大切になります。
では、こうした2つの軸をどのような制度設計・運用にすれば
実現ができるかを、次回以降のメルマガでお伝えしたいと思います。
続きが気になる方は、
次回の『第3回 介護の評価制度コラム ~導入すべき等級設計と賃金設計 編~』をぜひお読みください。
メルマガ内容を先取りしたい方は、
お手軽に受講できるWEBセミナー(有料)もございますのでぜひご覧ください。
【続きはコチラ▶】
第3回 介護の評価制度コラム
~導入すべき等級設計と賃金設計 編~
ダイジェスト動画 ★公開中★
【YouTube】にて内容の一部を限定公開!
介護特化の人事評価制度セミナー
評価制度に関するセミナー
この記事を書いたコンサルタント

三浦 基寛
介護業界のコンサルティングに特化。介護施設・有料老人ホームの『業務標準化』 『スタッフ定着・離職防止』『リーダー・管理者育成』を中心とした組織づくりや生産性向上のコンサルティングを得意とする。人手不足・採用難時代の中で、経営者・事業部長・管理者・リーダーといった法人内の各階層の役職メンバーを巻き込みながら、成功事例を基に手堅くコンサルティングを実施している