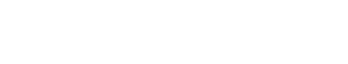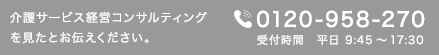【2025年】介護業界の現状と今後は?-時流予測をもとに行う経営とは-
- カテゴリ:
- 時流・業界動向
▼『介護業界 時流予測レポート 2025 ~今後の見通し・業界動向・トレンド~』 無料ダウンロードはこちら

介護業界が抱える課題と将来性
「2025年問題」に象徴されるように、日本の介護業界には様々な社会問題が密接に関係しています。労働人口は減少の一途を辿っており、その結果として介護現場では慢性的な人材不足が深刻な問題となっています。
この人材不足が深刻化する中で、介護人材の確保は年々困難になっています。人材不足の背景としては、仕事内容の負担が大きいにも関わらず、年収の水準が必ずしも高いとは言えない現状や、依然として高い離職率が、介護福祉士など専門性のある資格者の不足に拍車をかけているという実態があります。
本コラムでは、介護業界が直面する課題の現状を深掘りするとともに、働くすべての人にとっての将来性やキャリアパスについて、具体的な資料やデータを交えながら解説していきます。
2040年に向けて進行する高齢化
団塊の世代が75歳に差し掛かる2025年以降、日本の人口構造として、ますます高齢化が加速します。内閣府の『令和5年版高齢社会白書』によると、2022年時点で日本の総人口に占める65歳以上の割合は29.0%ですが、2040年には高齢者人口がピークを迎えると予測されており、それに伴い医療や介護サービスのニーズが急増し、国の社会保障制度を圧迫する可能性も指摘されています。
特に65歳以上の前期高齢者と比べ、75歳以上の後期高齢者に対しては、介護サービスの需要が格段に跳ね上がる傾向にあります。要介護(要支援)認定を受ける人口の割合が後期高齢者になると急激に高まるためです。結果として介護サービスの利用者が増え続け、介護事業所や介護職員の数が、利用者の数に追いつかなくなると見込まれています。利用者一人ひとりに質の高いサービスを提供するためにも、それを支える人材の確保が急務なのです。
高齢化が進む中で、求められる介護サービスの種類も多様化しています。特に近年、施設介護だけでなく、住み慣れた地域で生活を続けるための在宅介護サービスの需要が増大しています。そうした中で訪問看護など、看護師採用を始め、医療分野との連携を強化し質の高いケアを提供できる介護事業へのニーズは高まっていくと考えられます。こうした変化に対応できる柔軟な事業運営と、専門知識を持った人材がこれまで以上に期待されます。
介護業界で働く人材の現状
介護業界の人材不足を語る上で避けて通れないのが、給与や待遇の問題です。介護の仕事は、専門性とコミュニケーション能力、そして体力が求められる専門職ですが、その労働価値が給与という形で十分に評価されているとは言いがたいのが現状です。
厚生労働省が発表している『令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果』の資料によると、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は約318,230円でした。これは以前の調査と比較すると5,530円の増額となっており、国による処遇改善の取り組みが一定の効果を上げている実態もあります。しかし全産業の平均賃金と比較すると、介護職に対する給与待遇は依然として低い水準にあります。職種や保有資格、事業所の形態(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、訪問介護事業所など)ごとに給与水準は異なり、待遇にばらつきがあるのが現状です。
介護職員の給与の原資となるのが介護報酬です。近年、国は介護職員の処遇改善を目的として、介護報酬において介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算といった制度を設けています。これらの加算を取得するには、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があり、事業所側の積極的な取り組みが求められます。質の高いサービスを提供し、職員の待遇を充実させるためには、事業所がこれらの報酬制度を正しく理解し、事業所の状況に応じて利用しながら運営を行うことが不可欠です。
介護業界における今後の指針
①介護DXと科学的介護による生産性向上
人材不足を解決するために生産性の向上が求められる介護業界ですが、生産性の壁を突破する最大の鍵として期待されているのが、テクノロジーの活用、すなわち介護DX(デジタルトランスフォーメーション)です。
かつては介護に機械は馴染まないという声もありましたが、近年はそうした風潮が変わりつつあります。介護記録ソフトやスマートフォンアプリの導入は、情報共有を迅速化し、ペーパーレス化によって記録業務の負担を大幅に軽減しています。また、ベッド下の見守りセンサーやAIカメラは、夜間の巡視業務を効率化しつつ、利用者の離床や転倒リスクを早期に検知し、安全性を高めることが可能です。
さらに、移乗支援ロボットや入浴支援機器といった介護ロボットの種類も充実し、職員の身体的負担を直接的に軽減する効果が実証されつつあります。これらのテクノロジーは、職員が直接ケアという本来の専門性を発揮するための時間を創出する、強力なツールになっています。テクノロジーを導入し、それにあわせて業務フロー全体を見直すことが、事業所運営の生産性を飛躍的に高める可能性を持っているのです。
もう一つの変革として、科学的介護情報システム(LIFE)の活用があります。LIFEは全国の事業所から利用者の状態やケアの内容に関するデータを収集・分析し、その結果を各事業所にフィードバックする仕組みです。この情報を活用することで、自事業所のケアには全国の事業所と比較してどのような特徴があるのかを客観的に把握し、データに基づいたPDCAサイクルを回すことが可能になります。勘や経験だけに頼るのではなく、エビデンスに基づいたケアを実践することで、サービスの質向上と業務の標準化を両立させることが期待されています。
②多様な人材が輝くためのタスクシフティングと組織文化
人材不足への対応は、テクノロジーだけで完結するものではありません。人の働き方そのものを変革していく視点が不可欠です。
専門的な資格を持つ介護職員が、その専門性を最大限に発揮できる環境を整えるために、タスクシフティング(業務の移管)が注目されています。これは、配膳や下膳、清掃、リネン交換、備品管理といった直接ケア以外の周辺業務を介護助手やケアサポーターといった職種の人材が担う取り組みです。
これにより、介護福祉士などの専門職は、アセスメントや個別ケア計画の立案・実行、他職種との連携といった、より専門性が求められる業務に集中できます。これは、アクティブシニアや子育て中の主婦など、フルタイムでの勤務や身体介護は難しいが、短時間なら働く意欲があるという潜在的な労働力を社会で活かす道でもあります。無資格・未経験からでも介護の仕事に関連し、そのやりがいを感じてもらう入り口としても機能します。
EPA(経済連携協定)や技能実習、特定技能といった制度を通じて、外国人人材を採用することも介護現場の負担を削減する一手です。彼らが安心して長く働くためには、言語や文化の壁を取り除くためのサポート体制の充実が欠かせません。日本語教育や資格取得支援はもちろん、異文化を理解し尊重し合う組織文化の作り上げることが、定着率向上につながります。多様なバックグラウンドを持つ人材が集まる職場は、新たな視点や価値観をもたらし、組織全体の活性化にも繋がることが期待されています。
期待される介護業界の未来と人材
介護業界は人材不足や高齢化の進行といった大きな社会課題を抱えています。しかしそれは裏を返せば、これからの日本社会において最も必要とされ、成長が期待される分野であるということでもあります。
介護報酬の改定による処遇改善は今後も継続的に施行されていきます。そうした変化の中で介護職員それぞれの実務経験やスキルを適切に評価することは不可欠な取り組みです。経験やスキルが給与や各種手当の上昇という形で適切に反映される評価制度を導入することで、職員のモチベーションや介護サービスの質向上を進んで進める法人も増えてきています。
働きがいのある職場環境の整備やキャリアアップ支援を充実させることで、介護職の魅力やメリットを明確に示し人材の定着を図ることや、ICTの活用による業務効率化、外国人雇用による人材確保など、様々な面で対策が講じられている事例もあります。
これからの介護業界は、ただ人手が足りないから補充するというだけでなく、専門性を持った質の高いサービスを提供できる人材が中心となっていきます。自ら学び資格を取得し専門性を高めていく意欲のある人材にとっては、チャンスと活躍の場が広がっているのです。
トリプル改定を受けて 介護保険報酬改定 2025年
2024年には介護保険、診療報酬、障がい福祉サービス等の3つの保険制度・報酬が改定されました。介護保険報酬改定の大枠としては
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
2.自立支援・重度化防止に向けた対応
3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
4.制度の安定性・持続可能性の確保
5.その他
のカテゴリに分けて重点項目が設置されています。
今回の改定には従来の改定内容を踏まえて、より進化・推進、向上・改善させていこうというメッセージが込められています。
全体の改定率に関しては、+ 1.59%。そのうち、介護職員の処遇改善分+ 0.98%。
介護労働者確保のための処遇改善加算は1本化すると同時に若干アップする形式となりました。
基本報酬部分では、ほとんどの業態で報酬ややアップの傾向があります。
これは「経営状況に配慮しつつ」ということですので逆説的に考えると「経営がままならない事業所が増加している」と読み解くことができます。
経営が悪化!?介護事業所の数はいかに!?
厚生労働省の「介護サービス施設・事業所調査」によると、令和2〜3年にかけて「居宅介護支援事業所」数が237事業所も減っていることがわかります。
平成29年には48,235事業所あった「通所介護」に関しては令和2年には47,622事業所へ(マイナス376事業所)。
逆に急激に増えているのは「訪問看護」です。令和2〜3年にかけてなんと1,160事業所も増加しています。
「令和5年経営実態調査(厚生労働省)」によると、特別養護老人ホームが初めて「統計平均値」で「赤字」となってしまいました。
介護保険改定の「経営状況に配慮しつつ」という言葉は、こんな背景から来ているのかもしれません。経営がうまくいっている事業所と、そうでない事業所が2極化し、事業所のM&Aが活性化しつつあります。
2025年の介護業界はこうなる!
上記の現状を踏まえて、介護業界の今後には様々な変化がみられると予想されます。
「未来がどうなるか」これは誰しもが気になることかと思います。
改めて、2025年は介護業界においてどんな1年になるのか?
介護保険改定情報の気になる点も含め、我々、介護専門コンサルタントたちがよく耳にする情報を少し整理していきましょう。
・医療・介護連携の推進をどうすべきか
・処遇改善加算の一本化、採用につなげられる活用・配分ルールは?
・労働人口減・職員不足の状況に対応できる「介護人材戦略」
・介護保険事業にすべき新業態の立案
・変化に強く、幹部が育つ組織設計図は?
分かりきっていることだけでも、「明らかに時代が変わる」印象を強く受けます。
“時代の変化に対して、どう動くか?”
2025年は、法人としてのパワーを試される1年になりそうです。
これらの時流予測の詳しい概要は、下記ダウンロードレポートからご覧いただけます。
現在、高齢化の影響により「介護業界」の将来性が高まっています。
このことを踏まえ、自院のビジネスモデルを時流に合わせて構築したいと考える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、介護業界における現状と時流変化、介護業界の経営をする中で今後行うべきことについて詳しく解説いたします。
介護業界における現状と課題
介護業界を取り巻く環境には、様々な社会問題が絡んでいます。
こうした介護業界における現状と課題について、以下では2つの観点から詳しく解説します。
船井総研の「時流適応法」とは?
例えば、労働人口が減ってしまうことや、採用倍率が上がってしまうことを「変える」ことはできません。
ただし、採用条件を変更したり、求人文章・内容を「変える」ことはできます。
「変えられないことがある」ということを前提に「変えられること」を手掛けて事業所を進化させていく。
これが船井総研の「時流適応法」の基本です。
介護事業所が今後行うべきこと
船井総研の「時流適応法」を踏まえて、2025年に介護事業所がすべきこと(変えられること)をご紹介します。
それは、以下の3つです。
①稼働率を上げること
②職員の定着率を上げること
③事業推進力を上げること
では、実際にどう行動していけばいいのでしょうか?
ここからは、もっと詳しく、皆様に実施して頂きたいことをご紹介していきます!
◆稼働率・入居率を上げる
→「営業力」と「販促力」をつけましょう。
① 営業研修/販促研修をしましょう!
② ケアマネ営業「逃げずに」いきましょう!
◆職員の定着率を上げる
→ 組織風土の改革を行い「働きやすさ」と「働きがい」のある事業所を作る必要があります。
① 働きやすさ(勤務時間、待遇など)
L「誰かだけが都合の良い」職場になっていないか?確認しましょう。
問題があれば、そこを取り除きましょう。
② 働きがい(知識の共有、成長の機会など)
L仕事を通して得られる満足感を共有しましょう。
◆事業推進力を上げる
→ 幹部教育を行いましょう。
L研修受講を進める(自社でできなければ外部に依頼)
→ 差別化できる事業に進化させましょう。
L現在行っている事業で新規加算の取得、または新サービス創り、リニューアル
2025年を戦っていくためにも、上記の内容に関することに取り組んでいただくことをオススメします。
下記レポートには、介護業界の詳しい現状や具体的な取り組みなど、本記事よりも詳しい情報を掲載しています。
是非、無料ダウンロードをして2025年の時流予測を経営にご活用ください!
私たち船井総研としても上記に関わる情報を今年も1年間発信していく計画です。
今年1年も引き続きご愛読ください。
▼『介護業界 時流予測レポート 2025 ~今後の見通し・業界動向・トレンド~』 無料ダウンロードはこちら

この記事を書いたコンサルタント

管野 好孝
小売業の店長職を10年間経験。不振店の建直しを得意としてマネジメント業務に携わる。レンタル業界大手のTSUTAYAに着任後、たった1年で日本一に導いた実績を持つ。(ツタヤ・スタッフ・カンファレンス2009年) 船井総研入社後は介護業界に特化してコンサルティングを実施(詳しくは下部、コンサルテーマ参照)。経営者の「やりたいコト」に「伴走」したコンサルスタイルに定評があり「指名」を頂くケースが非常に多いコンサルタントである。(6年連続 指名数No.1)