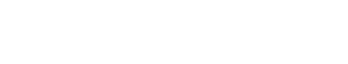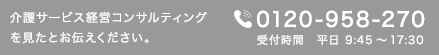年内3社限定!介護特化の営業研修+同行15件 50万円
- カテゴリ:
- その他
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
「営業がしたくて介護業界に来たわけではない」
この言葉が至極真っ当である介護業界においても、利用者獲得の活動は必須となっています。
デイサービスの数は今やコンビニの数以上とも言われており、
導入期・成長期・成熟期・衰退期の4つからなる”ライフサイクル”において、
介護業界では成熟期や衰退期に差し掛かっている業態もあります。
導入期であれば、サービスの真新しさから「開設するだけで人が来る」ということもありますが、
ほとんどの業態で商圏内に競合が存在し、
「近いから」という理由だけでは選ばれなくなっているのが現状です。
今回はそんな介護業界における正しい営業活動の実施方法についてお伝えします。
業態に関わらず、施設系・訪問系・通所系 あらゆる事業所にお役立ていただける内容を心がけて発信いたしますので、
是非お付き合いください。
営業から新規契約まで、成約率の業界平均は5%
皆様の事業所での利用者獲得の取り組みが上手くいっているかどうか、
その判断の基準の一つに成約率があります。
数多くの介護事業者様とお付き合いさせていただいてきた船井総合研究所が、
独自に設けた基準ではありますが20件の営業件数に対して1件の成約、が
業界の平均的な成約率です。
さらに分解すると、
営業→問い合わせ率は3割
問い合わせ→見学・体験率は5割
見学・体験→成約率 は約3割(およそ3分の1)
です。
場合によっては看取りまで対応する”究極のサービス業”とも呼べる介護業界では、
施設へ訪れた方や問い合わせに対する対応は親切丁寧な事業所様も多く、
問い合わせから成約までは高い、というケースをよく見かけます。
一方で、「問い合わせさえくれば・・」という問い合わせの件数自体が不足してしまっているケースも同じくらいよく見かけます。
利用者獲得でカギを握るケアマネ・病院からの問い合わせを増やすためには、
当たり前のことですが【より多くの居宅・病院とつながり】【自事業所のウリを正しく伝える】つまり量と質の両方が必要です。
外部と顔なじみになり、正しく伝える ということが苦手な方がいらっしゃるのもこの業界の特徴かと思います。
まずは量を確保することがおすすめなのですが、
営業活動として毎月40件以上ケアマネ・ソーシャルワーカーと接見できているでしょうか?
11時から16時までの訪問で20件は回れる
筆者自身、ご支援先の訪問営業活動に同行することがよくあります。
10時か11時頃に出発し、お昼は一緒に回る相談員の方と外でとり、
16時頃までの訪問でだいたい15件~20件は回れています。
件数に幅があるのは、ケアマネが不在の場合は1件あたりに係る時間が変わるためです。
1回あたり20件訪問するとして、これを月2回実施すれば40件です。
月にたった2日、「営業に行く日」を作って実行するということで、
それだけでも稼働率が上がっていく事業所も見てきました。
件数を2人で分担する場合であれば、1人につき月1回行くだけでOKです。
しかし、これがなかなかできない理由が数多く存在しています。
・「忙しくて営業の時間をとれない」
・「行って何を話したらいいのかわからない」
・「営業のやり方など教わっていない」
・「営業をしたくてこの業界に来たわけじゃない」 などなど
営業に行く時間については、シフトを組む段階で営業に行く日を決めましょう。
この日は現場業務はなるべく外してもらい、前述の11時~16時
または最低でも午前か午後のどちらか半日は外回りの時間を確保することです。
月末・月初はケアマネの請求業務があり、忙しい中話を聞いてもらえない可能性が高いため、
おおよそですが月の7日から25日くらいまでの間に日程を作り、
2週間後くらいに再度訪問(月2回の実施)できると理想的です。
営業で何を話したらいいかわからない、ということについてですが
これだけは伝えなければならないのは「空いていて受けられます」ということです。
ケアマネとしては、まずは空いているのかどうかを知りたいのです。
空き状況を伝えることは前提として、既存利用者の担当ケアマネに対しては利用者の状況報告を、
そしてまだお付き合いのないケアマネに対しては、「営業担当(相談員)のことを知って覚えてもらう」
ことに繋がる内容を伝えることです。
具体的には、
・初めましてのタイミングで人となりを伝える(職種や資格だけでなく、趣味などパーソナルデータを含める)
・顔写真(または似顔絵)つきの名刺を渡す
・同じ居宅には、同じ担当が行く(担当を固定し、繰り返し訪問することで顔を覚えてもらう)
このようなアクションです。
新規のケアマネに対する営業では、
・たくさんの事業所から営業を受けてうんざりしている
・知らない事業所からチラシなどもらっても正直見ない
・今忙しいのに聞いてもいない、知らない事業所の話をいきなりされている
正しいアプローチをしなければこんなネガティブな感情を抱かれてしまいます。
ケアマネが「紹介(問い合わせ)したい!」と思うまでには段階があり、
認知→興味→欲求→思い出す→行動(問い合わせる)→満足(紹介)という6段階です。
つまり、初めまして!の接見でいきなり問い合わせや紹介になるということはほぼないということです。
まずは相談員と事業所を知ってもらい、(認知)
その事業所の特徴を知り良いなと思ってもらい(興味)
プラン担当利用者にその事業所特性に合ったニーズが生まれ(欲求)
そういえばいつも来てくれるあの事業所なら対応してくれるかもと思い出し、
問い合わせる という段階です。
このケアマネの心の動きに合わせて、
初回訪問では詳細を語りすぎず、名刺交換・空き状況告知・何より人となりを印象付ける
2回目訪問では事業所のパンフレットを簡単に説明し、ここでも人となりを印象付ける(覚えてもらう)
3回目訪問でようやく事業所の特徴の話など少し詳細を話し、
4回目訪問では自事業所で実施する「モニター会(勉強会、症例発表会等呼び方様々)」イベントへ招待する
というのが船井総合研究所がおすすめする営業方法です。
最後のモニター会についてですが、毎回の訪問営業で話せる時間はせいぜい5分か長くても10分が限度です。
そんな短時間では、医療対応、認知症対応、設備、リハビリ内容、食事などなど、事業所の特徴を全て伝えることは不可能です。
そのため、しっかりと時間を取ってアピールを行うのがモニター会です。
しかしこのモニター会にも、いきなり来てもらえるわけではないため3回目か4回目くらいの訪問で招待、というのがセオリーです。
モニター会についてはまた次のメルマガでお伝えします。
ここまで、営業に行けない理由の解決に関してお伝えしてきました。
コンサルティングのご支援の中でも、こういった研修を実施しています。
船井総合研究所は「現場主義」「伴走支援」という考えを大切にしており、
研修だけで現場が変わるとは考えていません。
「研修は受けたけどそれでも行けるかどうか・・・」というのが実情です。
そのため、一緒に居宅や病院を回ってOJT形式でやり方を定着させます。
最初の数件は船井総研が手本として実施し、その後担当の方(目安2名)が順番に行い、移動の車の中でフィードバックします。
はじめはインターホンを押すのもためらうくらい不安な方もいますが、
実施した方のほとんどは
「ご利用者の担当ケアマネと久々に顔を合わせることができ、その大切さを知った」
「プラン担当利用者への対応についてお褒めいただき、モチベーションに繋がった」
「地域の居宅や家族、利用者が何を求めているかが確認できた」
こういったポジティブな反応をされます。
やってみると意外と簡単だったりして、最初の1回目さえ実施できればあとは自分たちでできるケースが半分くらいです。
今回はメルマガで伝えられる文字数の中で、実際にコンサルティングで伝えるノウハウをそのままお伝えできました。
伝えきれなかった内容もまだまだあります。
実際の研修では1時間から1時間半程度営業の全体像やポイント、トークスクリプトをお伝えしており、
午前中に研修後、実際に一緒に回ってみる(訪問営業同行)ということも行います。
今回メルマガをお読みいただいた方で、「【営業研修+訪問営業同行】の詳細を知りたい」という方につきましては、
メルマガ内のリンクから「無料個別相談(経営相談)」にお申し込みください。
貴施設の利用者獲得活動に関してあらゆるお悩みをご相談いただいたうえで、個別事情に合ったご提案を実施いたします。
先着3事業所まで営業研修・同行の年内実施を承っておりますので、ご希望の方に置かれましてはお早めにお申し付けください。
今回もメルマガをお読みいただきありがとうございました。
少しでも、今後の事業運営にお役立ていただけましたら幸いでございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
この記事を書いたコンサルタント