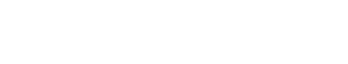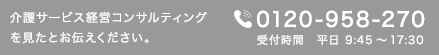【介護/障がい/保育】職員100名超の社会福祉法人様必見|離職を防ぎ、未来の施設長/リーダー候補を育てる「事業横断型」人事評価制度の作り方
- カテゴリ:
- その他
いつも コラムをご覧いただきありがとうございます。
船井総合研究所 福祉・保育グループ マネージャーの児玉です。
「時間をかけて大切に育てたつもりの職員が、また辞めてしまった…」
「施設長や主任ケアマネージャーといった中核人材が育たず、経営幹部や一部の職員に過度な負担がかかっている」
「毎年の処遇改善加算の支給が、結局はどんぶり勘定になっている」
「真面目に働く職員の士気まで下げてしまう『課題職員』の存在に、有効な手を打てずにいる」
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、デイサービスなどを運営されている理事長先生から、このような「人」にまつわる根深い課題をお伺いする機会が後を絶ちません。
とりわけ、介護・障がい・保育といった複数の福祉事業を展開する社会福祉法人様におかれましては、事業ごとの特性や収益構造の違いが、法人全体で統一感のある人事制度の構築を阻み、問題をより根深くしているという実情もございます。
これらの問題に対し、一時的な対処療法を続けても、根本治癒には至りません。法人の永続的な成長のためには、法人の理念・ビジョンに基づいた、戦略的な「人事評価制度」を構築し、着実に運用することが不可欠です。
本稿では、人材の定着と育成を両立させ、法人の未来を切り拓く人事評価制度のポイントを解説いたします。
なぜ、貴法人の「人事評価制度」は形骸化するのか?
処遇改善加算の取得をきっかけに人事評価制度を設けたものの、運用がうまくいかず形骸化している、というご相談は後を絶ちません。その背景には、多くの場合、以下の3つの典型的な失敗パターンが存在します。
① 汎用型
外部のテンプレートなど、どの事業にも当てはまりそうな一般的な評価制度を流用するパターンです。しかし、各事業の現場の実態に合わない項目ばかりでは「評価のための評価」に陥り、職員の成長を促すことはできません。
② 流用型
例えば、法人内で先に整備した保育園の評価制度を、介護事業にそのまま当てはめるようなパターンです。これでは事業ごとの「特例」が積み重なり、組織規模が大きくなるほど矛盾が露呈し、職員の不満の温床となりかねません。
③ 個別型
施設や事業所ごとに、全く関連性のない評価制度を運用するパターンです。法人内での連携が失われ、事業の垣根を越えたキャリア形成や幹部登用が不可能となり、多角化経営のメリットを享受できません。
制度の形骸化を回避し、真に機能する仕組みを築くには、まず人事評価制度の「目的」を明確に定義することが不可欠です。
人事評価制度の本当の目的は「給与査定」ではない
人事評価制度の目的を「職員の給与や賞与を決めるため」と捉えてはいないでしょうか。もちろんそれも機能の一部ですが、本質はそこにありません。
特に職員数が100名を超え、経営トップの想いが隅々まで行き渡りにくくなった組織において、人事評価制度が担うべき真の役割は、以下の2点に集約されます。
①管理者の発掘・輩出
法人の未来を牽引する管理職(施設長、管理者、リーダーなど)を、計画的に育て上げるための仕組みです。優れた管理者が育てば、新規施設の開設や、既存事業所の業績アップ/収益改善が可能となり、法人は次の成長ステージに進むことができます。
②課題職員の是正
法人の価値観や運営方針に非協力的であったり、チームの和を乱したりする職員に対し、制度という客観的なものさしで改善を求めるための仕組みです。これにより、誰もが安心して働ける職場規律を保ちます。
この2つの目的を達成するためには、「等級」「賃金」「評価」「研修」の4つの要素を有機的に連動させて設計することが、成功への絶対条件となります。
職員が育ち、定着する!「人事評価制度」4つのポイント
それでは、具体的に4つの制度それぞれの設計ポイントを見ていきましょう。
①等級制度:「管理職を目指したい職員」と「現場で働き続けたい職員」で道筋を分ける
全ての職員に、画一的なキャリアを求めるのは現実的ではありません。職員それぞれのキャリア志向に応じた道筋を用意することが重要です。
管理職を目指したい職員(キャリアアップ志向): 等級ごとに求められる役割と責任を明確化し、昇格へのルートを可視化します。これにより、向上心のある職員は迷うことなく、意欲的にキャリアアップを目指せます。
現場で働き続けたい職員(スペシャリスト志向): 高度な目標達成よりも、コンプライアンス遵守や協調性といった、組織人としての基本動作を評価の軸に据えます。これにより現場の安定性が高まり、全体のサービスレベルが向上します。
この考え方に基づき、例えば「新人指導担当」や「オペレーションリーダー」といった役割を等級と連動させることで、組織の力が底上げされます。
②賃金制度:「目指したい」と思える魅力的な処遇を示す
等級が上がると、どのようなメリットがあるのか。それを職員に分かりやすく示すことが不可欠です。例えば、管理職の給与水準を一般職の1.5倍に設定するなど、明確で魅力的なゴールがあるからこそ、職員は前向きに上位等級を目指すのです。
同時に、各等級に賃金の上限額を設定することも重要です。上限なき昇給は、長期的に人件費を圧迫するだけでなく、職員の挑戦意欲を削ぐことにも繋がりかねません。
③評価制度:「頑張る職員」を正しく評価し、「課題職員」にNOを突きつける
評価項目は「一般職員」と「役職者」で明確に分けるべきです 。
一般職員の評価:評価項目は10個程度に絞り込み、「出勤率(遅刻早退含む)」や「提出物遅延率」といった客観的データを必ず盛り込みます。そして最も重要なのが、自施設の「稼働率/入居率」や事業所の「売上予算達成率」といった経営指標を加えることです。これにより、職員に「施設経営への参画意識」が芽生えます。
役職者の評価:「売上予算達成率」などに加え、「顧客満足度」「職員満足度(エンゲージメント)」を評価軸に加え、より高い経営視点での貢献を求めます。
④研修制度:等級と研修を連動させ、成長を「仕組み化」する
各等級で必須となるスキルを習得するための階層別研修を整備し、全ての職員に公平な成長の機会を提供します。その際、サービスの質を標準化するために、等級別の「業務マニュアル」を研修テキストの核とすることが極めて効果的です。動画研修なども導入すれば、将来の事業拡大にも耐えうる、サステナブルな人材育成システムが構築できます。
さらに、管理者候補を対象とした「幹部カンファレンス(理事長塾)」などを定期開催し、経営のリアルな情報を共有することで、彼らの視座を現場から経営へと引き上げ、次世代幹部としての当事者意識を育みます。
「仕組み」だけでは不十分!職員の心を掴む「攻め」の人事戦略へ
ここまでお伝えした「等級・賃金・評価・研修制度」は、組織の土台を固めるための、いわば「守り」の制度です。
しかし、職員の働きがいを真に向上させ、組織に活気をもたらすためには、制度という土台の上に、金銭では測れない「承認」や、成長を後押しする「ポジティブな働きかけ」といった、「攻め」の人事戦略を組み合わせることが不可欠となります。
例えば、法人全体のビジョンを共有する「経営方針発表会」や、理念に沿った行動を全職員の前で称える「表彰制度」などは、職員のエンゲージメントを高め、組織の一体感を強める上で絶大な効果を発揮します。
「自法人の人事評価制度を、今度こそ根本から刷新したい」
「管理者育成の遅れと、課題職員への対応という長年の課題を、仕組みで解決したい」
「職員が誇りを持ち、長く働き続けたいと思える組織文化を醸成したい」
このような経営課題の解決を本気で目指す経営者の皆様へ、私たちのノウハウの全てを公開するセミナーをご用意しました。
【理事長先生向け】介護・障がい・保育 経営課題を解決する人事評価制度セミナーのご案内
本セミナーでは、コラムだけではお伝えしきれない、人事評価制度の設計から定着までの具体的なステップ、そして職員のエンゲージメントを最大化する「攻め」の人事戦略について、介護・障がい・保育の各業界に精通したコンサルタントが、成功事例を交えて詳しく解説いたします。
<このようなお悩みを抱える法人様におすすめ>
・「優秀な職員」の離職に歯止めをかけたい。
・他の職員の離職原因とさえなる「課題職員」を何とかしたい。
・管理者/施設長が不足していて、兼任職員が疲弊している。
・将来の法人を担う、事業を横断して活躍できる幹部候補を育てたい。
・既存事業の評価制度を、無理やり他の事業に当てはめている。
・事業間の評価制度や賃金制度に不公平感・不平等感がある。
・公平な評価基準がなく、結局どんぶり勘定になっている。
・処遇改善加算のキャリアパス要件の対応に悩んでいる。
・処遇改善加算のために評価制度を導入したが、形骸化している。
【開催概要】
開催日時:2025年10月21日(火)、31日(金)、11月10日(月)、28日(金)
いずれも13:00~16:00
開催形式:オンライン
【参加料金】
一般価格 30,000 円 (税込 33,000 円)/ 一名様
会員価格 24,000 円 (税込 26,400 円)/ 一名様
【介護・障がい・保育】を2事業以上営む社会福祉法人の理事長様必見
事業の壁を越え、法人全体で機能する
社会福祉法人のための人事評価制度の再構築
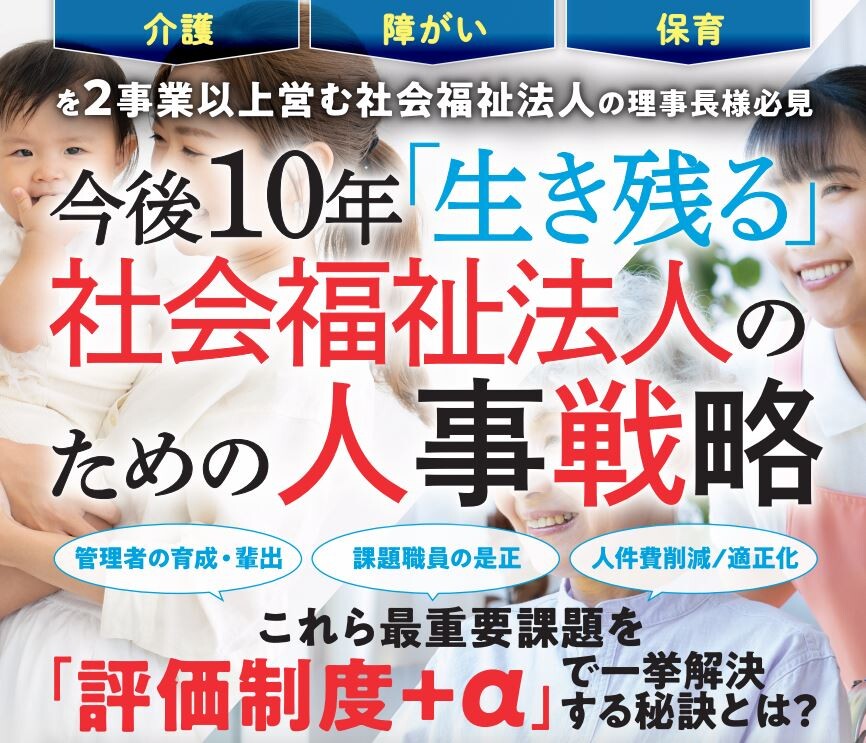
この記事を書いたコンサルタント

児玉梨沙
宮崎県出身。東京大学教育学部を卒業後、船井総合研究所に入社。 保育園や幼稚園などの子ども・子育て支援分野、そして児童発達支援・放課後等デイサービスや就労継続支援事業など、障がい福祉分野において、事業展開、マーケティング戦略、マネジメント戦略など、多岐にわたる分野でコンサルティングを行ってきました。 自治体の「こども計画」策定などにも携わっており、豊富な実績と、官民双方における幅広い経験に基づき、クライアントに最適なソリューションを提供します。