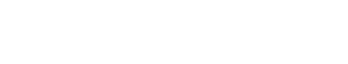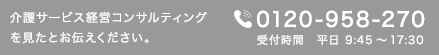「訪問介護の収益改善が難しい」「在宅での重度利用者対応に限界を感じている」—超高齢社会において、このような課題を抱える介護事業者は少なくありません。しかし、地域密着型サービスの可能性を信じ、制度開始当初から「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に積極的に取り組み、成功を収めている法人が兵庫県姫路市にあります。今回は、姫路医療生活協同組合(以下、姫路医療生協様)の専務理事 黒岩様、および統括責任者の稲田様に、サービス参入の経緯から黒字化の具体的な秘訣まで、詳しくお話を伺いました。
企業紹介
姫路医療生活協同組合様は、「その人らしく気持ちよく生きる」ことを法人の理念とし、在宅に特化した事業戦略を展開されています。2006年度から小規模多機能型居宅介護を姫路市内で最初に開始するなど、地域密着型サービスの役割を重視されており、現在では定期巡回・随時対応型訪問介護看護を4事業所で運営し、地域の在宅生活を支える中核的な役割を担っています。

「定期巡回・随時対応サービス東部」
Q&A形式
Q1.株式会社船井総合研究所 全国的にも導入が進まない中、貴法人が「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に参入された戦略的な背 景をお聞かせください。
A.黒岩様 当組合は、事業戦略として在宅に特化しており、超高齢社会を乗り越える上で地域密着型サービスの役割が非常に大きいと考えてきました。特に、全国的にも一人暮らしの方が増えていますが、この方々を夜間の安否確認を含めて継続的に支えるには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が最も適していると判断しました。 姫路市では、制度開始(2012年度)から3年間公募がありませんでしたが、私たちは参入の方針を固めており、2015年度に募集があった際に一番最初に手を挙げました。以降、地域に根差した実績を評価いただき、毎年の公募で指定を受け、現在4事業所を運営しています。このサービスは、法人の理念である「その人らしく気持ちよく生きる」ことを在宅で実現するために不可欠な事業だと位置づけています。
Q2.株式会社船井総合研究所 事業開始当初、特に課題となった点や、初期の職員様の反応はどのようなものでしたか?
A:稲田様 最も大きな課題は職員体制です。元々訪問介護を行っていた職員に、定期巡回特有の夜勤、オペレーター、計画作成責任者といった新たな業務を担ってもらうことになった際、職員の間では大きな不安が広がりました。 また、定期巡回はICT(情報通信技術)の活用がセットとなるため、それまで紙ベースで業務を行っていたベテランヘルパーからは「私できひんわ」という不安の声が上がりました。これを乗り越えるためには、若手職員がICT利用の指導や説明を担う必要があり、一時、まるでスマホ相談会のように、ベテラン職員が次々と操作を学びに来る状況でした。
Q3.株式会社船井総合研究所 サービス導入の際に生じた「20分」という時間に関する誤解と、それを克服した営業戦略についてお聞かせください。
A. 黒岩様・稲田様 サービス提供の目安として「20分」という時間が独り歩きし、「20分しか対応できない」という誤解が広がり、当法人の居宅介護支援事業所や職員の間で混乱が生じました。この誤解は、他の居宅介護支援事業所にも変な噂が流れてしまう原因にもなりました。 この誤解を払拭するため、特に後の事業所開設時からは介護度が高く、一人暮らしでご家族の支援も受けられない方には、排泄介助や食事介助で「1時間近く」の支援も可能であると明確に居宅介護支援事業所にお伝えしています。私たちは、自立支援の視点から、利用者さんができることはやっていただき、できないところをしっかりサポートするという考え方を浸透させていきました。
Q4.株式会社船井総合研究所 黒字化までの期間や、健全な運営を維持するための具体的なKPIについてお聞かせください。
A. 黒岩様 正直なところ、姫路市で最初に始めたためノウハウがなく、最初の事業所では黒字化までに3年から4 年を要し、非常に苦労しました。しかし、その後立ち上げた事業所(北部)では、約1年半から2年弱で黒字に転換できています。 健全経営を維持するための鍵となるKPIとして、私たちは利用者数(件数)30件にこだわり、営業活動に取り組んできました。現在、最も利用者数の多い東部事業所では48名の方にご利用いただいており、月商は約740万円で運営されています。利用者さんに喜んでいただけるとともに、うまく運営すればしっかり黒字も作れるサービスだと確信しています。
Q5.株式会社船井総合研究所 運営効率を向上させるために、人員配置や業務フローで工夫された点はありますか?
A. 稲田様 運営効率化の大きな転換点は、ヘルパーの配置の見直しでした。以前は訪問介護のヘルパーが定期巡回を兼務していましたが、短時間の安否確認(3分など)のために、訪問介護基準の移動時間の手当(15分など)を支給することが非効率でした。 現在は、訪問介護と定期巡回のヘルパーを概ね分け、事務所付けヘルパーを中心とした体制に移行しました。これにより、人件費の配分が改善し、最も収益性の高い東部事業所では、常勤換算11名で人件費比率が60%以下と低く抑えられています。
Q6.株式会社船井総合研究所 最後に、これから定期巡回への参入を検討される法人様へのメッセージをお願いいたします。
A.黒岩様 私たちも制度が始まったばかりの頃は、姫路市で最初の参入だったこともあり、ノウハウがなく「生みの苦しみ」を経験し、黒字化まで長い期間を要しました。しかし、今では全国でノウハウが蓄積され、研修会やセミナーも充実しています。 現在参入される法人様であれば、事前にしっかりと運営ノウハウを学ぶことで、当時我々が苦労した住み分けや立ち上げの課題を回避し、比較的早期に健全な運営が実現できると思います。 定期巡回は、在宅での生活継続を強く望む利用者様に対し、「複数回訪問」「何かあればいつでもつながる」という安心感を提供でき、利用者様に心から喜んでいただけるサービスです。超高齢社会において、地域包括ケアシステムを支える上で不可欠なこの事業に、ぜひ挑戦していただきたいと思います。