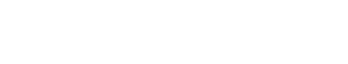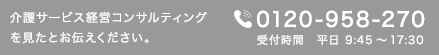介護は共生型の方向へ!?ビックリの事実
- カテゴリ:
- その他
こんにちは。
船井総合研究所の管野です。
近年、「共生型サービス」という言葉を耳にすることが増えました。
これは、高齢者も障がい者も、年齢や状態に関わらず同じ事業所で
サービスを受けられる、新しい介護の形です。
なぜ今、共生型が注目されているのか、その現状と未来について
見ていきましょう。
デイサービスで進む、共生型はすでに 2,000事業!?
特に目覚ましいのが、デイサービスにおける共生型サービスの広がりです。
厚生労働省の統計によると、なんと全国の通所介護事業所の約15%が
既に共生型サービスを展開しており、その数は年々増加の一途を辿っています。
国も2025年までに、共生型サービス事業所を2,000か所へ増やす目標を
掲げており、この流れはさらに加速するでしょう。
これは、従来の介護保険サービスと障害福祉サービスが別々に提供
されていた状態から、同じ事業所で両方のサービスを提供できるように
することで、利用者にとっても事業所にとっても、より柔軟で
質の高いケアが実現できることを意味します。
利用者は慣れた場所でサービスを継続でき、事業所は利用者層を広げ、
安定的な運営につながります。
サ高住でも進む共生の動き
デイサービスだけでなく、サ高住においても、同様の「共生」の兆しが
見られます。
直接的に「サ高住での共生型が増えている」という統計データは
まだ少ないものの、多世代が共生する住宅の事例は増えており、
その中には障がいを持つ方や医療的ケアが必要な方も含まれています。
サ高住にはデイサービスや訪問介護事業所が併設されているケースも多く、
こうした環境下で共生型サービスが提供されることは十分に考えられます。
高齢者も障がい者も共に暮らす社会を目指す中で、
サ高住がそのハブとなる可能性を秘めていると言えるでしょう。
ビジネスモデルチェンジと人材の共有化へ
この共生型の動きは、単なるサービスの追加に留まりません。
多くの介護事業所にとって、これはビジネスモデルの大きな変革を
意味します。
利用者層の拡大だけでなく、これまで別々に配置されていた介護士と
障害福祉サービスの職員が、同じ事業所で働くことで人材の共有化が
進む可能性も出てきます。
これにより、人材不足が深刻化する福祉・介護業界において、
より効率的かつ柔軟な人員配置が可能になることが期待されます。
職員は多様な利用者と接することでスキルアップにもつながり、
職場全体の専門性向上にも貢献するでしょう。
共生型サービスを視察するツアー開催決定!
本記事でご紹介した「共生型サービス」の具体的な成功事例を、
実際に見て、学ぶチャンスを船井総合研究所にてご用意致しました。
「介護・シニア事業者向け モデル企業視察ツアーin仙台」
多業態が融合した「介護×福祉×自費」の1棟完結型共生施設や、
介護×福祉×保育のまち創り型共生施設 を視察できます。
「ガイアの夜明け」にも出演した事例 や、地域の方が毎日100名
来訪する「まちの縁側」と称される複合型福祉施設「アンダンチ」
さらには138名のシニアが活躍する「街仲食堂」のビジネスモデルなど、
最先端の取り組みを肌で感じられる貴重な機会です。
詳細・お申し込みはこちらから!
このセミナーは、経営者や管理職の方々にとって、
未来の介護・福祉事業を考える上で大きなヒントとなるでしょう。
ぜひご参加をご検討ください。
【介護・シニア事業者向け】モデル企業視察ツアーin仙台
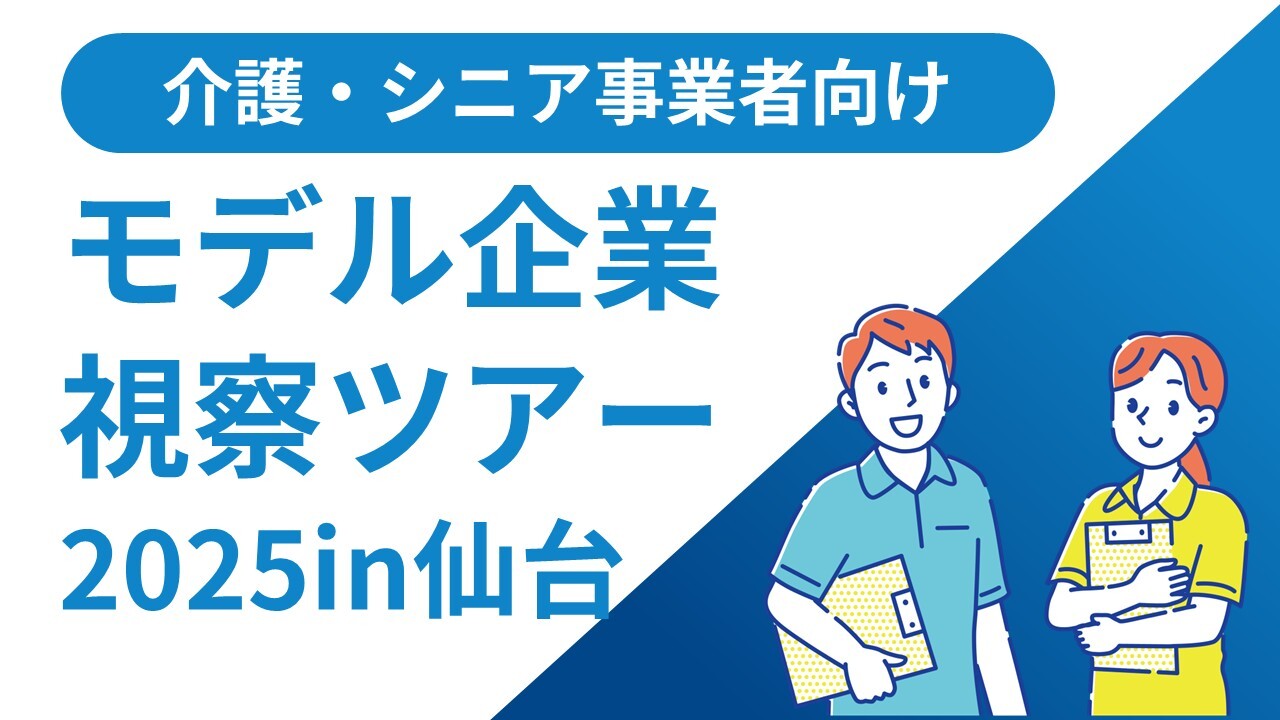
この記事を書いたコンサルタント

管野 好孝
小売業の店長職を10年間経験。不振店の建直しを得意としてマネジメント業務に携わる。レンタル業界大手のTSUTAYAに着任後、たった1年で日本一に導いた実績を持つ。(ツタヤ・スタッフ・カンファレンス2009年) 船井総研入社後は介護業界に特化してコンサルティングを実施(詳しくは下部、コンサルテーマ参照)。経営者の「やりたいコト」に「伴走」したコンサルスタイルに定評があり「指名」を頂くケースが非常に多いコンサルタントである。(6年連続 指名数No.1)