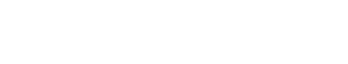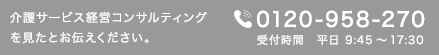いつもお世話になっております。
船井総合研究所の津田です。
さて、皆様も日々実感されているかと存じますが、近年、訪問看護ステーションを取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
・新規参入事業者の増加による競争激化
・看護師・療法士の採用難と人件費の高騰
・診療報酬・介護報酬改定による収益構造の変化
・利用者のニーズの多様化・高度化
かつて「やれば儲かる」と言われた時代は、もう終わりました。
こうした状況下で、「地域になくてはならないステーション」として持続的に成長し、質の高いサービスを提供し続けるためには、従来のやり方にとらわれない、戦略的な経営視点が不可欠です。
今回のコラムでは、この競争激化時代を生き抜くためのヒントとなる**「4つの経営戦略の柱」**について、5月の「【訪問看護】開設1年で利用者100人セミナー」にご登壇いただきます訪問看護ステーションを事例として、考えてみたいと思います。
競争激化時代で求められる3つの戦略転換
競争激化時代では、これまでの戦略から以下の3つの点での転換が求められます。
1.出店戦略:「とにかく開設」から、「特化や大型化による差別化、または新分野への進出」へ。
2.価格戦略:「価格戦略なし」から、加算算定による「高単価戦略」、またはコスト削減による「低単価戦略」へ。
3.販売促進戦略:「新規紹介者の獲得」から、紹介者との関係構築やリピーター育成を重視した「CRM(顧客関係管理)戦略」へ
開設1年で利用者100名達成!ひしょう訪問看護ステーションの戦略実践
人口7万人の町で立ち上げ1年で利用者数101名を達成(2023年10月時点)し、その後も利用者数を伸ばし続けている(2024年12月には139名)ひしょう訪問看護ステーションは、「治療だけ」ではなく”「生活の場まで入り込んだ」訪問看護ステーション”を目指して立ち上げられました。同社が実践された上記の戦略転換と、その他の成功要因を見ていきましょう。
1.出店戦略(特化)
城陽市にエリアを絞り込む「地域特化」戦略を採用。これにより、緊急対応やケアマネジャーとの高頻度なコミュニケーションが可能となりました。地域特化は、ケアマネジャーにとって「対応が早く、緊急時もすぐ駆けつけられる」「事務所でミーティングしやすい」といったメリットが大きいとされています。
2.価格戦略(低単価戦略の一部)
単価は低いものの、30分支援の訪問を積極的に実施することをベースとした料金体系としました。これにより、料金的に使い続けやすく、長期利用に繋がりやすくなるよう方針としています。30分訪問では、バイタル測定や内服管理は短時間で行い、残りの時間で本人ための個別的な支援を行うことが特徴です。
3.販売促進戦略(CRM)
開設当初はチラシ配布や挨拶回りを行いましたが、効果が見られない資料配布をやめ、代わりにiPadで支援動画を見せる、挨拶回りのタイミングをケアマネジャーが事務所にいる可能性が高いレセプト時期(8日、9日、10日)に統一する といった工夫を行いました。これにより、ケアマネジャーの困り事を直接聞く機会が増え、それに対して自分たちができることを伝えることで支援に繋がるようになりました。また、空き状況を伝えないことで問い合わせを促し、開設時からの既存のケアマネジャーを大切にする、新規からの依頼を断る場合も「枠がない」「人手不足」といった言い方ではなく、支援内容を確認してから断り方を工夫する など、顕在ニーズだけでなく潜在ニーズやインサイト(本人すら気づいていないニーズ)を理解し、相談役として足を運び続ける「一歩踏み込んだ営業」を実践されました。
ひしょう訪問看護ステーションのその他の成功要因
上記の戦略に加え、ひしょう訪問看護ステーションの成功には、以下のような要因が挙げられています:
・ケアマネジャーのニーズの理解・深耕
・利用者自身の「やりたいこと」を長期目標とし、自宅を「治療の場」ではなく「生活の場」と捉えた支援
・困難ケースを断らない
・関係事業所と「チーム」となる意識
・成長を支える人材の採用と育成
・LINEワークスを用いた迅速な報告・連絡・相談体制と情報共有
取り組みの詳細については、「【訪問看護】開設1年で利用者100人セミナー」でご紹介させていただきます。
ぜひ貴重な事例紹介セミナーを競争激化時代生き残りのヒントとしていただけたらと思います。
【訪問看護】開設1年で利用者100人セミナー
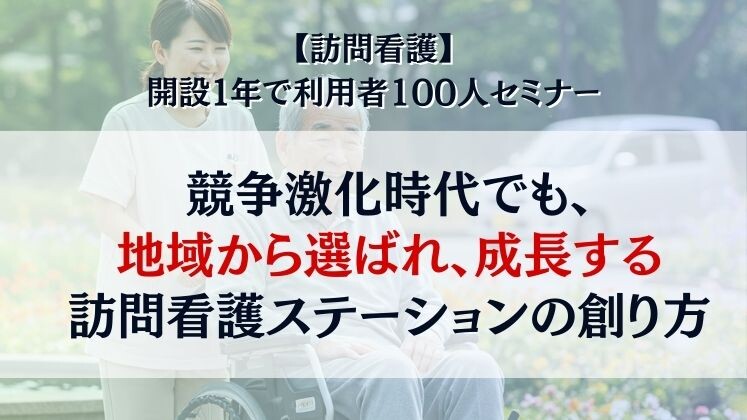
この記事を書いたコンサルタント

津田 和知
大手介護事業者の介護付き有料老人ホーム施設長を経て、船井総合研究所に入社。前職の経験を活かし、現場主義で問題の本質や改善の糸口を掴み、経営者のサポートを行う。コンサルティング領域は、介護施設の立ち上げや収支改善、訪問看護ステーションの立ち上げ、人事制度構築など。