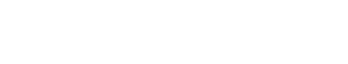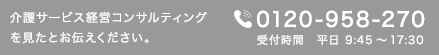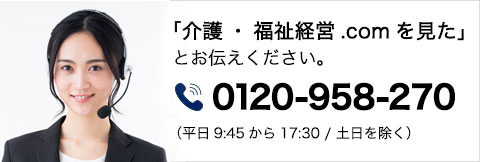共生型デイサービスで月商1,000万円を実現——就労支援連携で生まれた新しい経営モデル
利用者の確保が難しい——。しかも職員の確保も難しい——。
デイサービス業界では、事業所数の増加により利用者の取り合いが進み、稼働率の維持が大きな課題となっています。
こうした中で注目を集めているのが、障がい福祉と介護を一体的に提供できる「共生型デイサービス」です。
共生型の仕組みを活用することで、障がいのある方を新たな利用者層として受け入れ、安定した稼働を実現する事業所が増えています。
さらに一部の先進的な事業所では、就労支援事業を併設し、現場の人材確保や生産性向上にもつなげる取り組みが進んでいます。
今回は、その先駆けとして制度施行初期から共生型に取り組み、30名定員のデイサービスで月商1,000万円(就労支援を含む)・利益率20%を達成した「株式会社デイサービスセンターうららか(兵庫県加古川市)」の事例を紹介します。
【株式会社デイサービスセンターうららか 企業紹介文】
兵庫県加古川市を拠点に、介護・障がい・医療の3分野を一体的に展開する株式会社デイサービスセンターうららか。
代表の住所和彦氏は2010年に創業し、デイサービスを中心に、就労継続支援B型・訪問看護など多角的な事業を展開しています。
同社は2018年に共生型デイサービスの指定を受け、制度施行の初期からいち早く参入。理念である「老若男女、障がいの有無を問わず社会進出を応援する」を掲げ、高齢者と障がい者が自然に交わる“共生の場”を実現しています。
現在は、就労B型事業とデイサービスを連携させ、清掃や配膳などの間接業務を就労利用者が担うことで、介護職員は専門業務に専念可能に。
人材不足の解消と同時に、就労利用者の雇用・工賃向上も実現しました。
この仕組みにより、定員30名規模で月商1,000万円、人件費率50%を達成。地域の課題解決と事業成長を両立させたモデルとして、全国の事業者から注目を集めています。

(株式会社デイサービスうららか 代表取締役 住所様)
Q. 共生型デイサービスを立ち上げられた背景、特にそのきっかけについて教えていただけますでしょうか。
A.私たちの企業の理念は「年齢、性別、障害にかかわらず、社会進出を応援し、住むのは家、暮らすのは地域」というものです。
しかし、実際に高齢者デイサービスを運営する中で、高齢の利用者様が「家に帰ったら障害を持つ息子の世話をしなければならない」と話し、ご自身のデイサービス利用中にそのことが頭から離れず、また金銭的な負担を減らすため
にデイサービスでの昼食も召し上がらないという状況を目の当たりにしました。
これはまさに「老老介護」や、昨今よく聞かれる「5080問題」に通じる、非常に深刻な社会課題だと感じました。
ご家族が安心してデイサービスを利用し、かつ障害を持つ息子様も社会生活を遮断することなく地域で暮らせる環境を作るにはどうしたらいいか。
「これを使えるならやろう」と、この一連の出来事が共生型デイサービスの開設の最も大きなきっかけとなりました。

Q. 共生型デイサービスへの転換は、貴社の事業に具体的にどのような経営的なメリットをもたらしましたか。特に収益性や利用者様の層についてお伺いしたいです。
A. 転換後、デイサービスの一日型(定員10名から)を拡大し、現在は合計30名(一日型20名、半日型午前・午後各10名)で運営しております。一日型の定員20名はほぼ100%の稼働率を維持できており、そのうち障がい者(生活介護)の利用者様は4〜5名程度です。
売上比率で見ると、全体の月間売上(750万円~800万円)のうち、約13%から15%を生活介護が占めています。この生活介護での受け入れによって全体の稼働率と収益のベースが確保できており、結果的に営業利益率は最大で20%を推移しています。また、生活介護の利用者様の多くは、区分3から5といった重度よりの方々です。
さらに、利用者様のほとんどがグループホームからの利用となっており、日中活動の場を提供することで、新たな顧客層を獲得できています。
Q. 共生型への移行時、職員や既存の高齢者利用者様からの反発をどのように乗り越えられましたか。
A. やはり移行当初は反発がありました。
「なぜ障がい者の世話までしなければならないのか」「関わり方がわからない」といった声が多く上がったのは事実です。
これを克服するために、私たちは「標準化」と「教育」を徹底しました。まず、私たちの理念の根幹である「接遇」に関する指針である「接遇11カ条」を高齢者向けだけでなく、障害のある利用者様にも通用するよう「接遇11カ条
共生型運用版」として明文化しました。
これにより、関わり方や初動を間違うことで起こる拒否反応などを防ぐための具体的なマニュアルとして活用しました。
私たちは、現場で「何を頑張ったか」を定量化し、個人の責任にさせず、「会社の考え方が悪かった」と失敗を会社のマニュアルのせいにするくらいで良いと考えています。
毎日「65点」という当たり前の標準力を維持できるように、すべての業務(入浴、食事、排泄など)をマニュアル化し、週に一度は周知活動を行うことで、属人化を防いでいます。
Q. 貴社独自の強みとして、どのように質の高いケアを提供し、利用者様を獲得されているのでしょうか。
A. 弊社は訪問看護事業にも力を入れており、約30名の看護師が在籍しています。
この訪問看護部門の看護師が、デイサービスの職員に対し、社内研修という形で講師を務めてくれています。障害分野の対応が可能な看護師によるサポートや研修があるため、重度の方(区分3~5)でも安心して受け入れられるスキルを担保できています。
また、私たちは就労継続支援B型事業所も運営しており、就労Bの方々に業務委託という形でデイサービスの関節業務(食事の配膳、シーツ交換など)を手伝っていただいています。
これは、単なる労働リソースの確保(人件費効率化)になるだけでなく、生活介護の利用者様や高齢者利用者様と、就労Bの方々との間に心を通わせるコミュニケーションを生み出し、心の安心につながっています。
さらに、利用者様やご家族、そしてサービス提供者との理解を深めるために、モニタリングレポートに非常に力を入れています。
生活の様子を写真やQRコードによる動画、テキストで細かくカラーでレポートすることで、ご支援者様への情報共有を徹底しています。
Q. 貴重なお話ありがとうございました。今後、共生型デイサービスを検討されている介護事業所の経営者へメッセージをお願いします。
A. 共生型デイサービスは、社会生活の維持・継続を支えるという点で、非常に重要な役割を担います。
特に障がい者の方々が地域との関わりを持ち続けるための下支えとなり、最終的には高齢者になっても住み慣れた地域で暮らせるように支援していく。
時間がかかるかもしれませんが、一緒に見守っていくという形に違和感はなくなってきています。
そして、先述の通り、共生型は社会性のみではなく、十分な利益を確保するための下支えとなる数字が出ています。
収益化という観点からも、社会貢献という観点からも、取り組む価値は十分にある事業であると確信しています。
いかがでしたでしょうか。
本コラムでご紹介した「株式会社デイサービスセンターうららか」の住所和彦社長は、デイサービスと就労支援を融合させた経営モデルの先駆者として全国から注目を集めています。
この住所社長が登壇される特別セミナーでは、制度施行初期から取り組んできた経験をもとに、
・デイサービスの就労B型連携による人材確保・工賃アップの実例
・定員30名で月商1,000万円を実現した経営モデルの再現ポイント
など、記事ではお伝えしきれなかった実践ノウハウを詳しく解説いただきます。
「今後のデイサービス運営をどうしていけばいいか」「採算を取りながら地域に貢献できる仕組みを作りたい」そうお考えの経営者の皆様に、必ずヒントとなる内容です。
👇 詳細・お申込みはこちら
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/134765