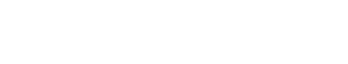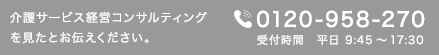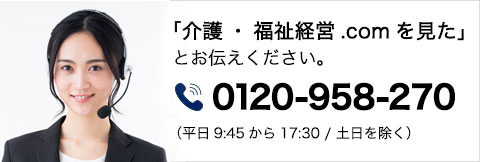全国でも希少──「高齢デイ×共生型放課後等デイ」一体運営の事例 特定非営利活動法人くるるに聞く
高齢者デイサービスの経営環境は、制度改定や人材難、地域内競争の激化により、かつてない厳しさを迎えています。稼働率や収支の改善に頭を悩ませる経営者が多い中、既存資源を活かしながら、持続可能なモデルへの転換を図る事業者も出始めています。 その一つが「共生型デイサービス」の活用です。介護保険と障がい福祉の制度を組み合わせ、 高齢者と障がい者が同じ空間でサービスを利用できるこの仕組みは、制度上の柔軟性を活かした新しい収益モデルとして注目されています。 今回は、その中でも全国におよそ150事業所しか存在しない、高齢者デイサービスと共生型放課後等デイサービスを併せて展開している、特定非営利活動法人くるる様の非常に珍しい取り組みをご紹介いたします。
<法人紹介>
特定非営利活動法人くるる様は、大阪市西淀川区にて、高齢者デイサービスと放課後等デイ サービス(共生型)を同一事業所内で運営されており、子どもから高齢者までがともに過ごし、支え合える共生の場を地域に提供されています。高齢者の方には、日常生活の延長線上で過ごせる環境の中、入浴や体操・レクリエーション通じて心身の健康維持を図るサービスを提供されており、お子様には、世代を超えたふれあいの中で成長できる居場所を届けておられます。また、地域住民と連携した「にしよどこども食堂くるる」を運営されており、子どもたちへの温かな食事提供や、地域とのつながりづくりにも積極的に取り組んでおられます。世代・立場・支援ニーズを超えた交流が日常的に生まれる“くるる”の取り組みは、地域福祉の新たなモデルとして注目されています。
Q1,特定非営利活動法人くるる様が共生型デイサービスを始められた経緯や、どのようなサービスを提供されているのか教えていただけますか。
A.私たちの法人は、もともとは子ども食堂の運営から活動を始めたんです。地域のボランティアメンバーの中に介護職の経験がある方が多かったことと、私自身もケアマネジャーとして勤務していることから、介護事業の展開を検討することになりました。 その際、市の知人から「共生型サービスとして放課後等デイサービスも併設可能」とアドバイスをいただきまして、そこで、地域密着型デイサービスと共生型放課後等デイサービスを運営することを決めました。背景としては、子ども食堂を利用されるご家庭の中には、発達障がいをお持ちのお子さんや、精神的に不調を抱える保護者の方もいらっしゃいます。そういう方々へ支援するためにも必要と考えた次第です。現在は、半日型のデイサービスとして入浴サービスを中心に提供しながら、子どもから高齢者まで多世代が自然に交流できる場所づくりに努めています。
Q2,共生型デイサービスならではの魅力や、既存のデイサービスとの違いは何でしょうか。
A.高齢者の皆様の中には、「長時間施設にいるのは負担に感じる」「運動には消極的」「高齢者ばかりの空間には抵抗がある」といったご意見をお持ちの方も少なくありません。そこで私たちは、高齢者デイサービスに子供たちが過ごす空間を活用することで、心理的なハードルを和らげられるようなサービスを提供しています。 たとえば、お子様と一緒に体操やレクリエーションを行うことで、「良いところを見せたい」というお気持ちが生まれ、自然と体を動かされる方もいらっしゃいます。また、子どもたちの明るい声が空間を和ませ、皆様の笑顔を引き出してくれる場面も多くございます。 子供たちと過ごす中で自然と、心から楽しいと感じていただける時間をご提供できているのではないかと思っております。
Q3,高齢者と障がいをお持ちのお子様が同じ空間で過ごすことで、どのような相乗効果が生まれるのでしょうか。
A.子どもたちと関わることで、高齢者の皆さんが「自分の役割」を見つけられて、生きる意欲の向上を実感しています。 中には、もともと通所を嫌がっていた認知症の方が、「子どもたちが来るから行かないと」と前向きな気持ちになって通所を希望されるようになったケースもありました。こうした変化は、結果的に通所の継続にも繋がっています。 また、職員の立場から見ても、子供と高齢者がお互い関わる時間を持つことで、職員のサポートが必要な時間が減り、ゆとりが持てています。こうした世代を超えた助け合いが自然に生まれるのは、私たちが大切にしている特徴のひとつだと思っています。
Q4,運営面で工夫されている点や、特に気を付けていることはありますか。
A.ご利用者の方には、安全で快適に過ごしていただけるように、時間帯や空間の使い方を工夫しています。たとえばお子さんの場合だと、高齢者の方が帰宅の準備をされている時間帯には勉強の時間を取ったり、高齢者の方が退室されたあとに広いスペースを使って体を動かす活動をしたりしています。動線や時間の使い方を少し工夫するだけで、お互いに快適に過ごせています。送迎に関しては、高齢者の方については基本的にドア・トゥ・ドアで対応しています。お子さんの場合は、自宅の前に保護者様に来ていただいています。また、他のご利用者の安全を第一に考えて、自傷や他害の行動が見られるお子さんについては、面談のときに丁寧にご相談させていただいた上で、お断りする場合もあります。 「安心して過ごせる環境づくり」が一番大事だと思っています。
Q5,サービスを開始する上で、集客やスタッフ教育など、どのような課題がありましたか。また、どのように克服されましたか。
A.集客の面では、まだ「共生型」という形態自体が広く知られていないこともあって、ケアマネジャーさんや相談支援専門員さんにもなかなか理解が進んでいないんです。そのため、ご紹介につながりにくいという課題は正直ありました。 ただ、私たちの事業所では、一度体験利用いただいた方がご契約に至る割合がとても高いんです。これは、スタッフの雰囲気だったり、子どもがいるので過ごしやすいからだと感じています。スタッフ教育については、もともと介護の知識を持った職員は多かったんですが、障がいの特性に対しては十分に理解できていなかったんです。そこで、障がい福祉の専門知識を持つスタッフを採用したり、外部研修を実施したり、終業後のミーティングで情報共有を重ねたりして、現場全体のスキルアップに取り組んできました。立ち上げ当初は利用者数も少なかったので、その時間を逆に活かして、じっくり事業の形を作り上げることができたのは、今では大きな強みになっていると思います。
Q6,共生型デイサービスの運営において、特に注意すべき点はありますか。
A.介護と障がいの両方のサービスを提供していると、やっぱり請求業務や事務処理の部分で課題が出やすいと感じています。例えば、今のところ介護と障がいの両方に対応できる請求システムが限られています。私たちの法人でも、介護保険と放課後等デイサービスの請求をそれぞれ別のシステムで管理していて、場合によっては手作業で対応しなければならないこともあります。その分、業務負担が大きくなりがちです。 それに、高齢者と障がい児とでは記録する項目が違うので、一方のサービスに特化したシステムではもう一方の業務がどうしても煩雑になってしまいます。 これから共生型に参入しようとされる事業者さんには、請求ソフトの選び方や事務体制づくりについて、十分に準備しておくことが大切ですよ、とお伝えしたいです。
Q7,今後、共生型デイサービスを検討されている介護事業者の皆様へ、メッセージをお願いします。
A共生型のサービスは、これからの社会でますます必要とされていく仕組みだと確信しています。多世代の交流や人と人とのつながりを求める声はたくさんあるんですが、実際にそれを実現できる場って、まだまだ少ないのが現状なんです。介護の世界では“縦割り”の意識がどうしても強く残っている部分があります。でも、実際に共生型を運営してみると、利用者さんや地域の方々の笑顔に触れるたびに、「やってよかったな」と心から感じます。 もちろん、始めるときは不安もあると思います。ただ、一歩踏み出していただければ、きっと多くの気づきや手ごたえが得られるはずです。 高齢者も子どもたちも、そして職員も活き活きと過ごせる…そんな共生型デイサービスという新しい形を、ぜひ検討していただけたらと思います。