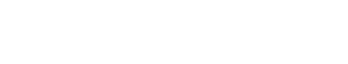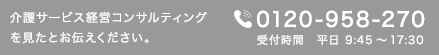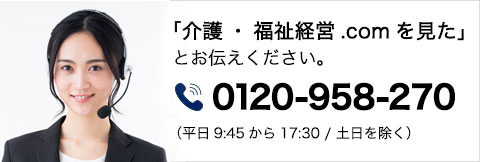【成功事例】収益改善の鍵は「共生型デイサービス」への転換!地域資源を活かした独自戦略で安定経営を実現
現在、デイサービス事業所数は40000件超え、特に地方では高齢者の減少に伴い、市場の競争が激化しています。
既存のデイサービス経営において収益の確保が難しくなりつつある今、共生型デイサービスは、人員や設備を大きく変えずに福祉サービスへ参入し、収益の安定化を図るための有力な選択肢として注目を集めています。
地域に根差した独自性の高いサービスを展開し、高い稼働率と安定した経営を実現されている合同会社太介さまに、共生型デイサービスの可能性についてお話を伺いました。
【企業紹介】
介護支援専門員(ケアマネジャー)や看護師の経験を持つ荒井あかね氏と、介護業界に約30年携わってきた菅野秀人氏の両代表社員が、地域課題の解決を目指して平成30年(2018年)に合同会社を立ち上げました。
地域に根差したデイサービスを展開するために共生型デイサービスを開設。空き家となっていた古民家を活用した「お家のような」デイサービス運営が特徴です。
Q1. 競争の激しい市場で、貴社が「共生型デイサービス」を選択した決定的な理由は何でしょうか?
A. 共生型デイサービスを選択した理由は主に三つあります。 一つは、地域において共生型を提供している事業所が非常に少なかったため、「唯一無二」の存在になれればと考えたことです。
二つ目は、地域には医療法人や全国展開しているような大きな法人様が多い中で、そうした大手にできないような独自の事業を、自分たちで実現したいという思いがありました。
そして三つ目は、個人的な背景として身内に障害者がいるため、将来的な介護問題を見据えた経験値を積み、それが地域のお役に立てればという考えもきっかけの一つです。 また、事業所として、空き家となっていた古民家という良い物件が見つかったことも大きな要因です。
Q2. 「古民家利用型」というユニークなコンセプトは、具体的にどのように初期投資や固定費の削減に貢献していますか?
A. 私たちは空き家となっていた古民家を賃貸で利用しています。
実は、この物件をかなり安価で借りることができており、これが経営の大きなカラクリとなっています。
初期投資や月々の固定費を極限まで抑えることができているため、売上に対して利益を確保できる構造となっているのです。
また、施設の改修についても、なるべく家の環境を活かすことを重視しました。バリアフリーにはわざとせず、玄関の段差や柱もそのまま残しています。
結果的に、改装に手を加えた部分はエアコン設置や、お風呂の段差解消のためのすのこ作り、車椅子対応のトイレ改装程度に留まっています。
Q3. 高稼働を維持する貴社の現在の収益構造と、特に障害福祉サービスがどのように貢献していますか?
A. 当事業所は定員8名に対し、稼働率が約80%で推移しており、月商は約100万円から110万円です。
職員体制は常勤換算2.2名で運営しており、人件費を売上の約65%(月約60万円台)に抑えています。
この体制と前述の低固定費(格安家賃)により、毎月5万円から10万円程度の営業利益を確保できています。
特に収益に安定貢献しているのが、毎日利用してくださる障害事業の利用者様です。現在、毎日利用されている4名のうち、2名が障害の方です。
生活介護サービス(共生型)の単価は一回のご利用あたり約8,000円、食事代を合わせて9,000円弱となり、高齢者デイサービスに比べて単価が高く、安定した収入源となっています。
Q4. 営業活動を積極化しなくても利用者を安定確保できる、貴社独自の「古民家デイサービス」の集客力について教えてください。
A. 私たちのコンセプトは、病院や施設といった老後のイメージを避け、利用者が「普通のお家」に来ている感覚で過ごせる環境を提供することです。
デイサービスに抵抗がある高齢者の方も、「普通のお家だから、あまり気兼ねなく敷居が低く入れる」という点で選ばれることが多いです。
また、家庭的なお食事を提供していることも強力なアピールポイントです。
パンフレットに載せた料理写真が、営業時の強い訴求力となっており、普通の田舎料理を家庭的だと評価していただくことが多く、これが集客に繋がっています。
Q5. 区分4や5といった重度の方(8050問題後半など)の受け入れは、運営上の難しさよりもメリットが大きいのでしょうか?
A. メリットは非常に大きいと感じています。
当事業所の障害の利用者様は、毎日ご利用いただいている2名が区分5(80歳、知的障害)と区分4(61歳、身体障害)の方です。
特に、高齢化が進み介護保険と障害福祉の両制度の隙間にある「8050問題」の後半のケースなど、他では対応が難しいニーズに対応できています。
彼らは毎日安定して通所してくださるため、収益が安定する上、単価も高いため経営基盤を強固にしています。
区分5の方(80歳)は身体介護も必要で、排泄介助や歩行介助を要しますが、高齢者介護と大きく異なるわけではありません。
重要なのは、一人の人間として特性を理解し、アセスメントをしっかり行うことです。
Q6. 高齢者と障害者が共生する空間が、利用者様や職員に与える最も大きな良い影響は何ですか?
A. 高齢者の方々は、加齢に伴い「あれもできない、これもできない」という喪失感を感じていることが多いです。
しかし、そこに障害の方がいることによって、高齢の方々の間に「社会的弱者を助けたい」という自然な役割関係が生まれます。
これは、認知症の方同士の関係とは異なる「助け合いの関係値」となるのです。
高齢者にとっては、誰かに必要とされ、役割を果たすことで達成感を感じ、生きがいにつながります。
他の事業所の事例では、高齢の方が自ら進んで障害の方のお手伝いをすることで、職員の負担が減ったという報告もあるほどです。
共生型への参入を検討される方へは、障害というキーワードに対し、偏見によるハードルを上げないでほしいと助言したいです。
利用者さんの特性とこだわりに着目し、自分の感情や気持ちに置き換えて支援すれば、対人援助という本質は高齢者介護と変わらないため、やりがいのある分野としてぜひチャレンジしていただきたいです。