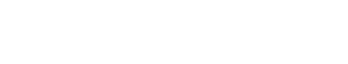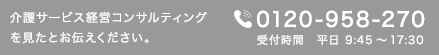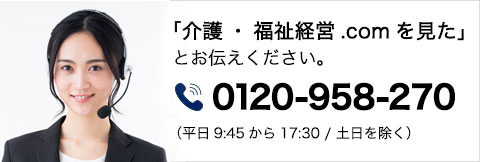デイサービス利用者の5割が障がいのご利用者!? 株式会社PEACEに聞く!共生型デイサービスの成功事例
近年、高齢者向けデイサービスは40,000件を超える事業所が存在し、競争の激化から集客に課題を抱える企業が増えています。そのような中、新たな事業モデルとして注目されているのが「共生型デイサービス」です。人員や設備を大きく変えることなく、障がいのある方も受け入れられる点で魅力的であり、高齢者デイサービスの経営にお悩みの皆様にとって、新たな可能性を拓く選択肢となり得ます。 今回は、全国的にもまだ少ない共生型デイサービスに積極的に取り組んでいる株式会社PEACE様、代表取締役の仲氏様に、その成功の秘訣について、株式会社船井総合研究所の介護経営コンサルタントが取材いたしました。Q&A形式で、共生型デイサービスの魅力と実践的な運営戦略に迫ります。 《法人紹介》 株式会社PEACE様は、堺市・河内長野市を中心に介護と障がい福祉の両分野で事業を展開する法人です。2016年の設立以来、「障がい⇔高齢の垣根を超えたケアをずっと。」を理念に掲げ、地域に根ざした包括的な支援を実践しています。 事業は今回お話をお伺いしました、共生型デイサービス「カラーピース」をはじめ、訪問介護「かなでヘルパーステーション」、居宅介護支援「ケアプランセンター シンプル」、相談支援「音色」、就労継続支援B型「カラーピース作業所」、サービス付き高齢者向け住宅「しきさい河内長野錦町」など多岐にわたります。高齢者も障がいのある方も分け隔てなく利用できる体制を整え、地域の暮らしを支えています。 企業理念の核となるのが「3つのPEACE」──①信頼の構築、②安心感の提供、③自己決定の尊重です。利用者に寄り添ったケアを徹底し、医療機関や地域団体との連携を深めながら、地域包括ケアの実現を推進しています。

(お写真:株式会社PEACE 代表取締役 仲氏様)
Q. 株式会社船井総合研究所
高齢者向けデイサービスの経営において、集客に課題を感じている企業が多い中、共生型デイサービスが注目を集めています。人員や設備を大きく変えることなく、障がいのある方も受け入れられる点で魅力的ですが、株式会社PEACE様が共生型デイサービスを始められた経緯について、まずはお聞かせいただけますでしょうか。
A. 仲氏様(株式会社PEACE 代表取締役)
私は約9年前、地域包括支援センター勤務時に「50-80問題」に直面しました。高齢者だけでなく、そのご子息が障がいをお持ちであったり、貧困などの課題があり、多様な支援が必要と感じました。国の「共生型社会づくり」の流れもあり、ワンストップで支援できる仕組みが重要だと確信しました。特に障がい者が65歳で介護保険へ移行する際、施設や職員が変わる問題を解決したかったのです。 そこで当社は「障がいから高齢までワンストップ支援」を掲げ、約6年前に共生型デイサービスを開設しました。コロナ禍で外出自粛の政策で高齢者の利用が減った一方、障がい者の利用が継続したことから、現在は利用者の半数が障がい者となっています。その7~8割は精神障がいを持つ50~60代で、入浴や居場所の提供に加え、内職など「仕事」のニーズにも応えています。この経験から、共生型は事業の持続性にも有効であると実感しています。
Q.船井総研
高齢者と障がい者の利用割合が半々で、特に精神障がいをお持ちの方が多いというお話、大変興味深いです。これは一般的な傾向とは異なるように思えますが、精神障がいの方が利用されることによる運営上のメリットや、職員様の負担感についてはいかがでしょうか?
A. 仲氏様
当社利用者の約7~8割は精神障がいをお持ちで、特に50~60代の方が多く利用されています。精神障がいの方はADLが自立している方が多いため、職員の負担は「見守り」と「一部介助」が中心で、重度の知的障がいや身体障がいの方と比べて身体介護の負担が軽減されています。また、精神障がいの方は季節によって波はあるものの、内職などの活動に意欲的に参加され、会話も活発です。そのため、職員も人としての関わりを大切にしながらサポートできています。 さらに、入浴や居場所の提供に加えて「仕事」のニーズにも応えられており、在宅生活が可能なほど安定している方が多いため、週2~3日の利用でもキャンセル率は低めです。同じ建物で運営している就労継続支援B型の利用者と比べても、デイサービスの精神障がいの方は安定している傾向が見られます。
Q. 船井総研
高齢者向けデイサービスでは収益性の確保も大きな課題となっています。月間の売上や営業利益がどのように推移されているのか、具体的な数値でお聞かせいただけますでしょうか。また、特に収益を安定させる上でどのような点がポイントになっているとお考えですか?
A. 仲氏様
当社デイサービスは定員30名で、平均稼働率8割、良い時は8割5分と安定しており、月間売上は最大610万円ほどです。介護報酬と障がい福祉サービス報酬はそれぞれ約300万円ずつで、構成比はほぼ半々です。 安定した稼働と収益の要因は、まずADLが自立している精神障がいの方が多く、利用が継続的でキャンセル率も低いことです。収益面では、生活介護の基本報酬(693単位)が区分2~6で共通な上、送迎・食事体制・看護師常勤・サービス管理責任者配置・入浴支援などの加算を組み合わせることで、介護保険サービス利用と同等の単位数を確保できます。 人員配置は常勤4名とパートを含め計8名程度に加え、送迎員をシルバー人材で補っており、人件費は月250万円未満で人件費率も50%を切ります。さらに建物はデイサービスと2階の就労継続支援B型で賃料を按分しており、全体で月約60万円に抑えられます。その結果、デイサービスと作業所を合わせて月250万円前後の営業利益を確保でき、これは業界でも珍しい高収益構造だと考えています。
Q. 船井総研
御社では共生型デイサービスだけでなく、就労継続支援B型事業所を併設され、さらには地域でのイベント開催やパン屋さんの事業承継など、多角的な事業展開をされていますね。これらの取り組みが共生型デイサービスの集客や事業運営、ひいては地域共生社会の実現にどのように貢献しているのか、詳しくお聞かせいただけますでしょうか?
A. 仲氏様
当社は1階で共生型デイサービス、2階で就労継続支援B型を運営し、親は介護保険サービス、子は就労支援と、親子が同一建物でサービスを利用できる仕組みを提供しています。これにより「50-80問題」の解決につながり、就労利用者が高齢や体調変化で働けなくなった際も、デイサービスへ移行できる連携性があります。 集客面では営業よりも地域との「顔の見える関係性」を重視し、「つむぎの会」として自治会・行政・医療福祉関係者と月1回の会議や交流を実施。国も共生型社会=まちづくりを掲げており、こうした活動が相談支援事業所やケアマネージャーからの紹介につながっています。 また、年1回「食を通じた町おこし」イベントを開催し約3,000人が来場致します。キッチンカーを活用し、障がいのある方と商品開発・販売を行っており、以前販売しました「台湾風かき氷」は300食完売致しました。 このような取り組みを通じて、地域のお祭りや高齢者施設でも交流の場をつくっています。さらに地域のパン屋の事業承継を行い、障がい者が袋詰めやシール貼りを担う機会も提供しています。こうした多角的な取り組みを通じ、障がいのある方が地域で役割を持ち、自己肯定感を高めながら生活できる社会を目指しています。
Q. 船井総研
共生型デイサービスへの転換を検討されている事業者様にとって、介護職の経験しかない職員が障がい分野の知識を持つ利用者様に対応することへの不安は大きいと思います。御社では職員の皆様への研修や教育について、どのように取り組んでいらっしゃいますか?
A. 仲氏様
ご心配は理解しています。私も介護一筋でやってきましたが、会社設立と同時に障がいヘルパー指定を取得し共生型を始めた当初は手探りでした。まず私自身が請求から運営まで全て経験し、その後管理者、主任へと段階的に業務を引き継ぐピラミッド型で体制を構築しました。これにより、業務領域が重なり合い、誰かが辞めても他の職員や最終的に私がカバーできるリスクヘッジができています。 現場を叩き上げてきた経験から、職員がつまずきやすい点も想定でき、具体的なアドバイスも可能です。研修という形ではありませんが、対人援助では「人としての深み」が重要であり、障がいも介護も含め、100人いれば100通りの対応があります。正解はなく、日々試行錯誤しながら利用者と向き合うことが大切です。うまくいく時もそうでない時もあると受け入れることで、支援側も気持ちが楽になります。体系的知識以上に、イレギュラー対応力や人間性こそが問われる仕事だと考えています。
Q. 船井総研
最後に、共生型デイサービスへの転換を検討している事業者の方々に向けて、成功の秘訣やアドバイスをいただけますでしょうか。また、株式会社PEACE様の今後の事業展開についてもお聞かせください。
A. 仲氏様
共生型デイサービスを検討される方は分からないことも多いと思いますが、まずは「やってみる」ことが大切です。運営の中で課題に直面しても、一つひとつ解決する過程が経験と知識となります。大事なのは「勇気」と「やってみる自信」、そして「こうしたい」という明確な思いです。それが事業を磨き、発展させる原動力になります。 今後は就労継続支援の分野に大きな可能性を感じています。労働人口が減少する中で、障がいのある方が「働き手」として役割を担える仕組みづくりは重要です。働けることが自己肯定感や自信につながり、社会貢献と事業の安定を両立できると考えています。 私にとって事業運営は「車の両輪」です。収益性だけでも、思いだけでも前進できません。両者のバランスを保つことが、株式会社PEACE、そして共生型デイサービスを成功に導く最も大切な要素だと確信しています。