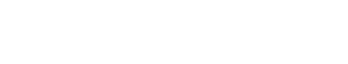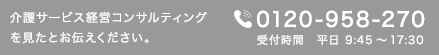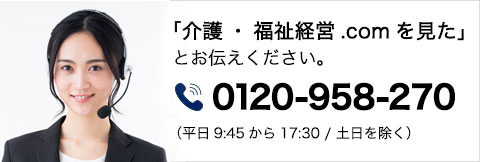在宅介護の未来を拓く:合同会社ふくえいの定期巡回成功事例 - 高収益と利用者満足度を両立する秘訣
超高齢社会を迎える日本において、在宅介護のニーズはますます高まっています。その中でも「定期巡回随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回)」は、利用者様の安心した在宅生活を支える重要なサービスです。
しかし、まだ全国に1300事業所ほどしかなく、「定期巡回は収益化が難しい」と感じている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、全国的な定期巡回随時対応型訪問介護看護の成功事例企業である合同会社ふくえい様に、定期巡回事業の収益改善に繋がる成功の秘訣を徹底取材しました。
合同会社ふくえい様は、新潟市を中心に3つの定期巡回事業所を展開し、高い利用者満足度と収益性を両立されています。今回は、合同会社ふくえい様の代表 笹川様、そして現場を支える大久保様から、具体的な取り組みや考え方をQ&A形式でご紹介いたします。
Q.船井総合研究所:御社が定期巡回サービスを開始された理由についてお伺いできますでしょうか?従来の訪問介護ではなく、定期巡回を選択された背景にはどのようなニーズがあったのでしょうか?
A.笹川様 : 単純な理由からですね。従来の訪問介護はどうしてもサービス内容に縛りが多く、ケアマネージャーさんや包括支援センターの方々から「もっと柔軟な訪問介護はないか」というご相談をいただくことが多かったんです。
私たちは以前、小規模多機能型居宅介護事業所に勤めていたのですが、通いが中心となるため、やはり訪問のニーズが高いと感じていました。
そこで、24時間対応可能な訪問サービスである定期巡回を立ち上げれば、従来のヘルパーでは対応しきれない部分をカバーでき、利用者様が少しでも長く在宅で生活を継続できるようになるのではないかと考えたのがきっかけです。
Q.船井総合研究所:定期巡回サービスを実際に導入されるにあたって、何か苦労された点や、当初の課題などはございましたでしょうか?
A.笹川様 : まず感じたのは、ケアマネージャーさんの意識改革が必要だったことです。どうしても従来の訪問介護のイメージが強く、私たちの定期巡回のサービスが、必要な時に必要なサービスを提供し、効率的に次の方へと繋がる点を理解していただくのに時間がかかりました。
一回の訪問でじっくりと時間をかけてコミュニケーションを取ることを期待されるケアマネージャーさんもいらっしゃり、定期巡回の特性である「必要なサービスを短時間で提供し、複数回訪問する」という点が、なかなか理解されませんでした。
Q.船井総合研究所:そうしたケアマネージャーの方々の理解を深めるために、具体的にどのような取り組みをされたのでしょうか?
A.笹川様 : 月末月初に実績を配布する際に、直接ケアマネージャーさんに対してサービス内容や請求について丁寧に説明するように心がけました。
まだ手探りで定期巡回を利用されているケアマネージャーさんも多かったため、制度のルールなどを一つ一つ丁寧に説明し、疑問点には新潟市に確認を取りながら回答するようにしていました。
Q.船井総合研究所:具体的なサービス内容に関して、ケアマネージャーさんからどのような質問や不明点が多く寄せられましたか?
A.大久保様 : 具体的なサービス内容になってくると、「どこまでやって良いのか」という線引きに関する質問が多かったですね。例えば、ご家族と同居されている方の生活援助など、従来の訪問介護では対象とならないようなケースで、定期巡回では柔軟に対応できる場合があるのですが、その判断に迷われるケアマネージャーさんがいらっしゃいました。
また、料金体系についても、従来の「一回いくら」という考え方ではなく、「月額包括」であることを理解していただく必要がありました。入院した場合の利用料の取り扱いなど、明確な基準がない部分については、市町村との連携を図りながら、事業所としての判断基準を設けて説明していました。
Q.船井総合研究所:初期投資についてお伺いします。定期巡回事業所を一つ立ち上げるのに、平均してどのくらいの資金が必要となるのでしょうか?
A.笹川様 : 一番最初に定期巡回サービスを立ち上げた際は、設備費や車両費、指定を受けるまでのスタッフの人件費などに、だいたい1,500万円ほど使いました。
Q.船井総合研究所:事業所の立ち上げから、単月で黒字化するまでには、どのくらいの期間がかかりましたか?
A.笹川様 : 新潟市南区の事業所のケースで言えば、令和元年の10月にオープンしたのですが、実はスタート時点から黒字でした。ただ、11月、12月に入院される方が多発し、一時的に赤字に転落しましたが、3ヶ月後の3月には再び黒字化しました。
元々運営していた自費の介護サービス事業所の利用者様に、定期巡回サービスへと移行していただいたことが、早期黒字化の大きな要因だったと思います。
Q.船井総合研究所:現在、3つの事業所を展開されているとのことですが、それぞれの事業所の平均月商はどのくらいでしょうか?
A.笹川様 : 南区の事業所を南区、西蒲区の事業所に分割する形にしましたが、分割前の事業所では、月商900万円ほどでした。現在は南区、西区、西蒲区の3つの事業所に分かれており、西区の事業所が600万円前後、南区と西蒲区の事業所がそれぞれ450万円ほどです。
Q.船井総合研究所:単独型の定期巡回事業所として、月商900万円というのは非常に素晴らしい数字だと思います。高収益を維持するための要因は何だとお考えでしょうか?
A.大久保様 : 登録者数も重要ですが、それ以上に重度の方やターミナルケアが必要な方の割合が高いことが、高単価・高売上に繋がっていると思います。短期間でのご利用となる方もいらっしゃいますが、そうした方への質の高いサービス提供が、結果的に全体の売上を押し上げていると考えています。
Q.船井総合研究所:現在の3つの事業所における、平均登録者数はどのくらいでしょうか?
A.大久保様 : 各事業所、入院中の方も含めると30名から40名ほどです。実動数で考えると、全体で100名程度になります。
Q.船井総合研究所:人件費率についてお伺いします。御社では、人件費率をどの程度に抑えられていますか?
A.大久保様 : 昨年度(令和 5 年度)の実績で、およそ 60%です。
Q.船井総合研究所:訪問介護員の方々は、一日あたり平均して何件くらいの訪問をされていますか?
A.笹川様 : 一人あたり、多い日で 16 件から 17 件ほどですね。距離などを考慮すると、平均して12 件から 15 件程度になるかと思います。10 件を下回ることはほとんどありません。
Q.船井総合研究所:効率的な訪問を実現するために、何か工夫されている点はありますでしょうか?
A.大久保様:ケアマネージャーさんとの密な連携と、利用者様のアセスメントをしっかりと行うことが重要です。必要なサービスを見極め、効率的な訪問計画を立てることで、移動時間のロスを減らし、より多くの利用者様へのサービス提供を可能にしています。
例えば、訪問介護であれば洗濯が終わるまで待っている間に別の作業をするというケースがありますが、定期巡回の場合、洗濯機を回している間に別のご利用者様のところへ訪問し、戻ってから洗濯物を取り込むといった、柔軟な対応が可能です。
Q.船井総合研究所:3 つの事業所を連携させて運営されていますが、連携によってどのようなメリットがありますか?
A.大久保様 : 管理事業所を中心に連携型で運営することで、急なヘルパーの欠員などがあ った場合でも、他の事業所から応援体制を組むことができ、安定したサービス提供に繋がっています。また、ノウハウや事例を共有することで、全体のサービス品質向上にも繋がっています。
Q.船井総合研究所:採用にお困りの事業所様は多いですが、御社で採用について何か工夫をされている点はありますか?
A.大久保様 : 採用媒体は、主にハローワークなどで行っていますが、特に注力しているのはリファラル採用で、紹介してくれた職員と入職者に紹介料をお渡ししています。待遇面では、より高い処遇改善加算を取るようにしています。これらを通じて、職員が「頑張れば給料が上がる」と頑張れる仕組みづくりを行っています。
Q.船井総合研究所:今後の事業展開について、どのような展望をお持ちでしょうか?
A.笹川様 : 現在、新潟市内の 3 つの区で事業展開していますが、今後は他の区にも少しずつエリアを広げていきたいと考えています。無理な拡大は避け、地域に根差した、質の高いサービス提供を継続していくことが目標です。
.船井総合研究所:最後に、これから定期巡回事業への参入を検討されている方や、収益改善を目指している経営者の方に向けて、何かメッセージをお願いいたします。
A.笹川様 : 定期巡回は、従来の訪問介護とは異なる特性を持つサービスです。まずはその特性をしっかりと理解し、ケアマネージャーさんとの密な連携を築くことが成功の鍵となります。
また、利用者様のニーズに合わせた柔軟なサービス提供を心がけることで、利用者満足度を高め、結果的に収益向上にも繋がるはずです。
大変な面もありますが、在宅で生活したいと願う高齢者の方々を支える、非常にやりがいのある仕事です。ぜひ積極的にチャレンジしていただきたいと思います。