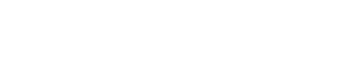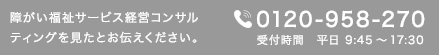就労継続支援B型事業者必見!就労選択支援について
- カテゴリ:
- その他
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
株式会社船井総合研究所の岩井でございます。
令和7年10月より、就労継続支援B型の新規利用希望者は原則として「就労選択支援」の利用が必要になります。この新制度は、障がいを持つ方が自分に合った働き方をより良く選択できるよう支援することを目的としています。この記事では、就労選択支援の概要から、B型事業者が知っておくべき具体的な対策までを解説します。
就労選択支援の概要
就労選択支援とは、障がいのある方が、自身の希望や就労能力、適性に合わせて、より良い就労先や働き方を選べるように支援するサービスです。これまでの制度では、一度就労継続支援A型やB型の利用が始まると、その事業所での利用が固定化されやすいという課題がありました。就労選択支援は、この課題を解決し、利用者が次のステップへ進む機会を適切に提供することを目的としています。
◆就労選択支援の主な支援内容は以下の通りです。
・短期間の生産活動などを通じた、就労に関する適性や能力、希望などの評価
(アセスメント)
・利用者や関係機関を集めての多機関連携によるケース会議の開催
・アセスメント結果の作成と共有
・関係機関との連絡調整
・地域の就労支援に関する情報収集と、利用者への情報提供
◆利用対象者と期間
就労選択支援の利用対象者は、就労移行支援や就労継続支援の利用を希望する方、またはすでに利用している方です。特に、就労継続支援B型の新規利用希望者(50歳に達している方や障害基礎年金1級受給者などを除く)は、令和7年10月から原則として就労選択支援の利用が必要になります。支援期間は原則として1か月で、利用日数の上限は各月の暦日から8日を引いた日数となります。支給決定期間の延長は原則として想定されていませんが、一度だけ1か月の再支給決定が認められる例外もあります。
◆報酬と運営基準
就労選択支援の基本報酬は、1日あたり1,210単位です。算定対象となるのは、利用者が直接支援を受けた場合や、利用者が同席するケース会議、企業訪問などです。
実施主体は、就労移行支援または就労継続支援を運営している障害福祉サービス事業者で、過去3年間に合計3人以上の一般就労移行者を出している必要があります。人員配置については、定員10人以上とし、管理者1名、就労選択支援員は15:1の配置が必要です。
就労継続支援B型事業者が取るべき対応策
就労選択支援の開始は、B型事業所の利用フローに大きな変化をもたらします。今後は就労選択支援を経由する新たな流れが主流となります。この変化に対応するため、就労継続支援B型事業者は積極的に対策を講じる必要があります。
◆関係機関との連携強化
新制度では、就労選択支援事業所や相談支援事業所が利用者の入口となるため、これらの機関との連携が不可欠です。
◆周辺事業所の把握
地域の就労選択支援事業所や、その他の関係機関(相談支援事業所、ハローワークなど)を把握し、連携を強化することが不可欠です。自事業所の情報提供だけでなく利用開始後の状況を定期的に共有することで、より強固な連携が築けます。
◆相談支援事業所への訪問
就労選択支援事業所と同様に、相談支援事業所も利用者からの相談が多くなると予想されます。定期的に訪問し、事業所の特徴や強みを伝え、関係性を構築することが重要です。
◆独自の強みの明確化と周知
就労選択支援を利用する方は、様々な事業所の情報を比較検討します。その中で選ばれる事業所になるためには、自事業所の強みや特徴を明確にし、それを積極的にアピールすることが重要です。
◆ウェブでの情報発信:Instagramなどを活用してウェブでの情報発信を強化し、事業所の認知度を高めましょう。多くの人に情報を届けることで、就労選択支援の利用を経て自事業所に興味を持ってもらう機会を増やせます。
終わりに
令和7年10月からの就労選択支援の導入は、就労継続支援B型事業者にとって大きな変化の機会となります。これまでの「待ち」の姿勢から「攻め」の姿勢へと転換し、積極的に情報収集や関係機関との連携を進めることが成功の鍵です。
新制度への対応は、事業所運営の在り方そのものを見直すことにも繋がります。今から準備を始めることで、新制度へいち早く対応し、事業の成長へと繋げることができます。
就労選択支援についてさらに詳しく知りたい方、今後のB型経営の具体的な計画や戦略を立てたい方は、ぜひ下記セミナーをご活用ください。新制度に対応するためのノウハウや今後の就労継続支援B型経営の在り方について知ることができます。
【就労選択支援を意識し、就労継続支援B型事業所が対応すべき内容のセミナーはコチラ】
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/133520
2年で就職32名!就労継続支援B型経営者が知るべき展望と戦略
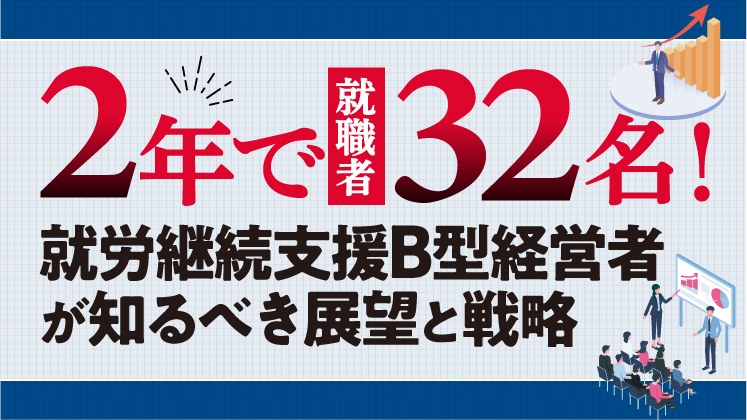
この記事を書いたコンサルタント

岩井 愛斗
大学卒業後、船井総合研究所に新卒入社。 現在は障がい福祉業界専門のコンサルタントとして、 主に就労支援事業や障がい者グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスの新規開業、業績UP、事業活性化を担当している。 また、WEBサイトや生成AI活用、SNS運用による採用・集客支援も得意としている。 経営者と現場の双方に寄り添う支援を目指している。