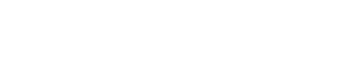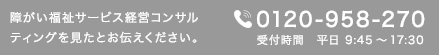【障がい/介護/保育】職員100名超の社会福祉法人様必見|離職を防ぎ、未来の管理者/サビ管/児発管候補を育てる「事業横断型」人事評価制度の作り方
- カテゴリ:
- その他
いつも コラムをご覧いただきありがとうございます。
船井総合研究所 福祉・保育グループ マネージャーの児玉です。
「時間をかけて育成したはずの有望な人材が、またしても辞めてしまった…」
「管理者やサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が育たず、理事長や一部の管理者に業務が集中している」
「毎年の福祉・介護職員等処遇改善加算の配分が、場当たり的な対応になっている」
「他の職員のモチベーションまで下げてしまう『課題職員』への対応に頭を悩ませている」
児童発達支援や放課後等デイサービス、就労継続支援、グループホームなどを運営される経営者の皆様から、このような「人材」に関する深刻なお悩みをいただく機会が非常に増えています。
特に、障がい福祉・介護・保育など、複数の事業を手がける社会福祉法人様の場合、事業ごとに働き方や収益モデルが異なるため、法人全体で一貫性のある人事制度の構築は容易ではありません。その結果、問題がより一層複雑化しているケースも散見されます。
これらの課題に対して、その場しのぎの対策を繰り返しても、根本的な解決には繋がりません。法人の持続的な発展を見据える上で重要なのは、法人の理念を核とした、戦略的な「人事評価制度」を設計し、確実に運用していくことです。
本コラムでは、職員の定着と成長を促進し、法人の未来を支える人事評価制度の要点について解説します。
なぜ、貴法人の「人事評価制度」は形骸化するのか?
福祉・介護職員等処遇改善加算への対応を機に人事評価制度を導入したものの、実際にはうまく機能せず形骸化している、というお声も頻繁に耳にします。その原因は、多くの場合、以下の3つのパターンのいずれかに当てはまっています。
① 汎用型
どの事業でも使えそうな一般的な評価テンプレートをそのまま導入するパターンです。しかし、事業ごとの実態に即していない項目が多く、「評価のための評価作業」に終始し、職員の成長意欲を引き出すには至りません。
② 流用型
例えば、法人内で最も歴史のある介護施設の評価制度を、新たに開設した児童発達支援事業所に無理やり適用するようなパターンです。結果的に事業ごとの「特例措置」が乱立し、組織が拡大するほどに矛盾が噴出。職員間の不公平感の温床となります。
③ 個別型
事業所やサービスごとに、全く異なる評価制度を運用するパターンです。これでは法人内での連携が生まれず、事業の垣根を越えた人材交流や幹部登用が進みません。複数事業を運営するシナジー効果を全く活かせない状態に陥ります。
制度の形骸化を回避し、真に機能する仕組みを築くには、まず人事評価制度の「目的」を明確に定義することが不可欠です。
人事評価制度の本当の目的は「給与査定」ではない
「人事評価制度とは、職員の給与や賞与額を決めるためのもの」、そうお考えの方も多いかもしれません。もちろん査定も重要な機能の一つですが、それは本質的な目的ではありません。
特に職員数が100名を超え、経営者の理念や想いが全職員に直接届きにくくなった組織において、人事評価制度が果たすべき真の目的は、次の2つです。
①管理者の発掘・輩出
法人の未来を担う管理職(施設長、サビ管、児発管など)を、計画的に育成するための仕組みです。優秀な管理者が育てば、新規事業所の開設やサービスの質の安定化が実現し、法人は更なる成長ステージへと進むことができます。
②課題職員の是正
法人の理念や方針に協力的でない、あるいは周囲の士気を下げる職員に対し、制度に基づいて客観的に改善を促すための仕組みです。これにより、健全な職場環境を維持します。
この2つの目的を達成するためには、「等級」「賃金」「評価」「研修」の4つの要素を戦略的に連動させて設計することが、成功への絶対条件となります。
職員が育ち、定着する!「人事評価制度」4つのポイント
それでは、具体的に4つの制度それぞれの設計ポイントを見ていきましょう。
①等級制度:「管理職を目指したい職員」と「現場で働き続けたい職員」で道筋を分ける
全ての職員に、一律で管理職を目指させる必要はありません。職員一人ひとりの志向性に合わせたキャリアパスを用意することが重要です。
管理職を目指したい職員(キャリアアップ志向): 等級ごとに担うべき役割・責任・権限を具体的に定義し、キャリアの道筋を明示します。これにより、成長意欲の高い職員は明確な目標を持って、スピード感あふれる成長を遂げることができます。
現場で働き続けたい職員(スペシャリスト志向): 高度な成長意欲よりも、組織のルール遵守やチームワークといった、組織人としての基本姿勢を重視します。これにより現場の秩序が保たれ、意欲ある職員が安心して働ける環境が整います。
この考え方に基づき、例えば「新人指導担当」や「オペレーションリーダー」といった役割を正式な等級として設定することで、組織全体のサービス品質が向上します。
②賃金制度:「目指したい」と思える魅力的な処遇を示す
等級が上がることで得られるメリットを、職員に分かりやすく提示することが極めて重要です。例えば、管理職の年収を一般職員の1.5倍程度に設定するなど、明確で魅力的なゴールがあるからこそ、職員は上位等級を目指す健全なモチベーションを維持できます。
また、各等級に賃金の上限(キャップ)を設けることも忘れてはなりません。上限なく昇給し続ける仕組みは、人件費を過度に圧迫するだけでなく、職員の健全な成長意欲を停滞させるリスクもはらんでいます。
③評価制度:「頑張る職員」を正しく評価し、「課題職員」にNOを突きつける
評価項目は「一般職員」と「役職者」で明確に分けるべきです 。
一般職員の評価: 項目は10項目以下に厳選し、「出勤率」や「各種提出物の期限遵守率」といった客観的な指標を必ず含めます。そして最も重要なのは、自事業所の「稼働率」や「売上予算達成率」などを評価項目に加えることです。これにより、職員一人ひとりに「事業所の経営に参画している」という当事者意識を育むことができます。
役職者の評価:「売上予算達成率」などに加え、部下の成長支援や定着率、チームワークの向上といった「組織貢献度」を評価軸に加え、より高い経営視点での貢献を求めます。
④研修制度:等級と研修を連動させ、成長を「仕組み化」する
各等級で求められる知識・スキルを習得するための階層別研修を設計し、全職員に公平な成長機会を提供します。その際、業務の標準化と効率化を図るために、等級ごとの「業務マニュアル」を整備し、研修の核とすることが不可欠です。いつでも学べる動画研修なども活用すれば、将来の事業拡大にも対応できる、持続可能な人材育成基盤が完成します。
さらに、管理者候補を対象とした「幹部カンファレンス(理事長塾)」などを定期的に開催し、経営方針を直接伝えることで、彼らの視座を現場レベルから経営レベルへと引き上げ、未来の経営幹部としての自覚を醸成します。
「仕組み」だけでは不十分!職員の心を掴む「攻め」の人事戦略へ
ここまでご紹介した「等級・賃金・評価・研修制度」は、いわば組織基盤を固めるための「守り」の人事制度です。
しかし、職員のエンゲージメントを真に引き出し、組織を活性化させるには、この制度という土台の上で、金銭的報酬以外の「承認」や、成長を後押しする「働きかけ」といった「攻め」の人事戦略が欠かせません。
例えば、法人全体の理念やビジョンを共有する「経営方針発表会」や、模範となる行動をした職員を全社で称賛する「表彰制度」*などは、職員のエンゲージメントを高め、組織の一体感を醸成する上で非常に有効です。
「自法人の人事評価制度を、今こそ抜本的に見直したい」
「管理者育成と課題職員への対応を、仕組みによって解決したい」
「職員のエンゲージメントを高め、持続的に成長できる組織を創りたい」
このような経営課題をお持ちの経営者の皆様のために、私たちの実践的ノウハウを凝縮したセミナーをご用意いたしました。
【理事長先生向け】介護・障がい・保育 経営課題を解決する人事評価制度セミナーのご案内
本セミナーでは、コラムではお伝えしきれなかった、人事評価制度の設計から運用までの具体的な手法、そして職員のエンゲージメントを高めるための「攻め」の人事戦略について、障がい福祉・介護・保育業界で多くの法人様のコンサルティング実績を持つ専門家が、余すところなく解説します。
<このようなお悩みを抱える法人様におすすめ>
・「優秀な職員」の離職に歯止めをかけたい。
・他の職員の離職原因とさえなる「課題職員」を何とかしたい。
・管理者/施設長が不足していて、兼任職員が疲弊している。
・将来の法人を担う、事業を横断して活躍できる幹部候補を育てたい。
・既存事業の評価制度を、無理やり他の事業に当てはめている。
・事業間の評価制度や賃金制度に不公平感・不平等感がある。
・公平な評価基準がなく、結局どんぶり勘定になっている。
・処遇改善加算のキャリアパス要件の対応に悩んでいる。
・処遇改善加算のために評価制度を導入したが、形骸化している。
【開催概要】
開催日時:2025年10月21日(火)、31日(金)、11月10日(月)、28日(金)
いずれも13:00~16:00
開催形式:オンライン
【参加料金】
一般価格 30,000 円 (税込 33,000 円)/ 一名様
会員価格 24,000 円 (税込 26,400 円)/ 一名様
【障がい・介護・保育】を2事業以上営む社会福祉法人の理事長様必見
事業の壁を越え、法人全体で機能する
社会福祉法人のための人事評価制度の再構築
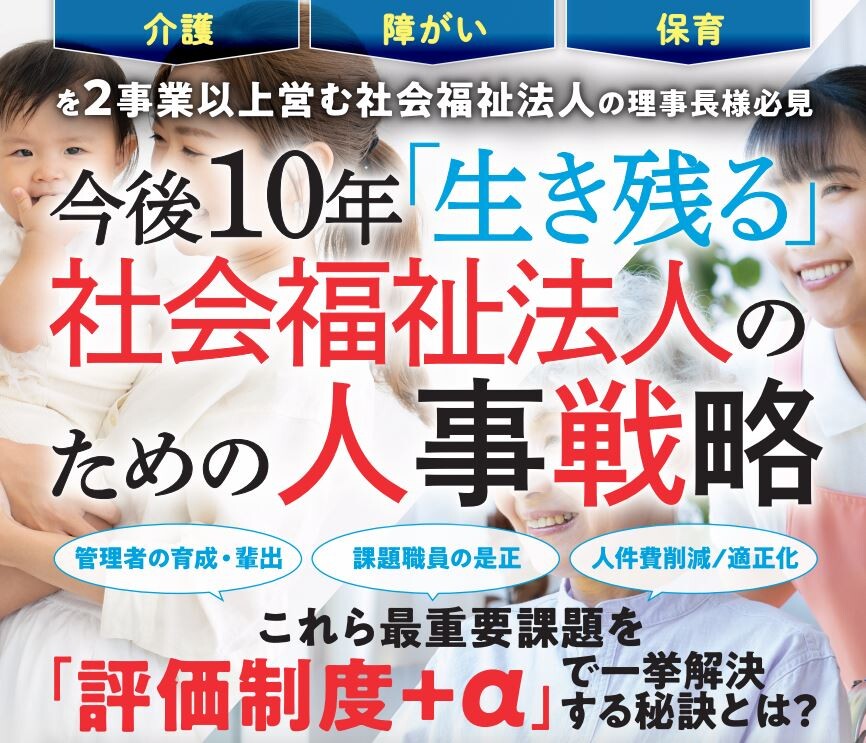
この記事を書いたコンサルタント

児玉梨沙
宮崎県出身。東京大学教育学部を卒業後、船井総合研究所に入社。 保育園や幼稚園などの子ども・子育て支援分野、そして児童発達支援・放課後等デイサービスや就労継続支援事業など、障がい福祉分野において、事業展開、マーケティング戦略、マネジメント戦略など、多岐にわたる分野でコンサルティングを行ってきました。 自治体の「こども計画」策定などにも携わっており、豊富な実績と、官民双方における幅広い経験に基づき、クライアントに最適なソリューションを提供します。