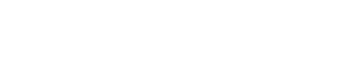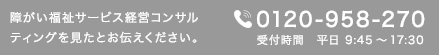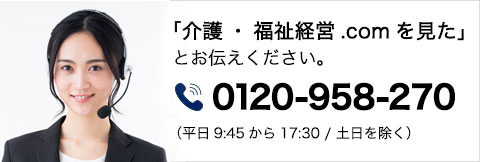全国的にまだ少ない「共生型デイサービス」の成功の秘訣とは?
高齢者デイサービス経営の安定化と地域ニーズの充足を両立させる合同会社シャイン様の取り組み
全国のデイサービス事業所数は40,000件を超え、競争の激化や2040年問題を見据えた将来的な需要の先細りといった経営課題に直面する企業が増えています。
こうした状況において、介護保険と障害福祉のサービスを一体的に提供する「共生型デイサービス」は、社会的な要請に応えつつ、収益性を確保する新たなビジネスモデルとして大きな注目を集めています。
今回は、全国的にまだ少ない共生型デイサービスに積極的に取り組み、地域に根差した福祉サービスを展開されている合同会社シャイン様(岩手県北上市)の佐藤様に、株式会社船井総合研究所の介護経営コンサルタントが、その成功の鍵と、高齢者デイサービスからの転換を検討する経営者様への具体的なヒントについて詳しくお話を伺いました。
【合同会社シャイン 企業紹介文】
岩手県北上市を拠点に、介護と障がい福祉の2分野を一体的に展開する合同会社シャイン。代表の古川尊之氏は長年にわたり介護現場で経験を積み、「行きたくないデイサービスを、行きたくなる場所へ変えたい」という想いから2021年に創業しました。
同社は共生型デイサービスの理念をいち早く実践に移し、年齢や障がいの有無を越えて誰もが自然に交わる“共生の場”を実現。
利用者が自ら「したいこと」を選び、笑顔で過ごせる時間づくりにこだわっています。
また、支援者が一方的に介助するのではなく、「共に楽しむ・共に挑戦する」姿勢を重視。地域行事や創作活動などを通じて、利用者・家族・職員が三位一体で関わる温かなコミュニティを形成しています。
こうした取り組みにより、利用者満足度と職員定着率の両立を実現。共生型デイサービスが持つ“地域共生の可能性”を体現するモデル事業として、注目を集めています。
Q1.デイサービスの需要が飽和する中、貴社が共生型デイサービスを開設された事業戦略の根拠を教えてください。
A1.介護事業だけでは2040年問題以降、需要が先細りしていくという見通しがあったため、比較的需要が安定している障害福祉サービスにも手を広げる必要があると考えました。
また、地域の障害をお持ちの方々の中で、重度な方向けの「生活介護施設」と、働くことに特化した「就労支援施設」のちょうど間にいる、在宅でゆっくり過ごしたいというニッチなニーズを持つ方が多いことが分かっていました。
同じハードウェア(施設)で異なるソフトウェア(サービス)を提供できる共生型であれば、この隙間産業的なニーズを満たせると判断しました。
Q2.開設初期に職員や利用者からの反発はありましたか。
A2.弊社の場合は、共生型で運営することを前提に新規開設と採用を行いましたので、スタッフから「聞いていなかった」というような表面的な反発はほとんどありませんでした。
利用者様に関しても、新規開設のため最初から定員が埋まるわけではなく、高齢者と障害者の両方が徐々に増えていったので、特に違和感なく受け入れていただけました。
ただし、近年は認知症の高齢者の方の利用も増えてきており、より多様な方々が集まる場となっています。そのため、利用者同士が安心して過ごせるよう、座席配置を工夫したり、利用前にお互いの状況を丁寧に共有するなど、より良い関わりが生まれるような調整を行っています。
Q3.職員採用や育成において特に工夫された点は何でしょうか。
A3.採用においては、「介護現場に長く浸ってきた人(例えば30年選手など)」を注意深く採用しないという方針をとっています。
経験豊富な方ほど、障害者へのケアに対して「やったことがないからできない」という反応を示すことが多かったためです。
むしろ、介護経験が10年程度までの方や未経験者、比較的若い方など、チャレンジング精神が旺盛な方を中心に採用することで、高齢と障害のどちらにも区別なく対応できる体制を築きました。
研修は内部研修が主で、基本的な知識を教えた後は、個別のケースバイケースでトライアンドエラーを通じて対応力を磨く形をとっています。
Q4.現在ご利用されている障害者の方々の主な特性や年齢層を教えてください。
A4.現在ご利用いただいている障害者の方の構成比は、精神障害の方が一番多いです。
全体の半分程度を占めています。ご年齢は40代の方が多いです。主な疾患は統合失調症などですが、基本的には症状が落ち着いた方々を受け入れています。
また、知的障害の方も今年の春に支援学校経由で初めて1名(19歳)いらっしゃいました。
Q5.障害者の方の利用促進のために、どのような営業戦略が効果的でしたか。
A5.最近はあまり積極的な営業ができていませんが、毎月問い合わせや紹介をいただけています。特に効果的なのはグループホームへの営業です。
弊社の事業所がある北上市周辺ではグループホームが非常に増えており、入居者様の日中活動先を求めているケースが多いからです。
障害福祉サービスの場合、介護保険のケアマネジャーとは異なり、相談支援員(ケアマネに相当)にサービス調整の厳密な決定権がないため、利用者ご本人やご家族、そしてサービス提供元であるグループホームと直接関係性を築くことが非常に重要になります。
Q6.これから共生型デイサービスを始める経営者へのアドバイスをお願いします。
A6.共生型デイサービスへの参入の敷居自体は低くなっています。しかし、特に福祉先進地域ではない地域だと、行政自体が共生型の制度をよく理解していないケースがあります。
私たちも手探りで始めた結果、何が正解か分からずにトライアンドエラーを繰り返し、時間的なロスがありました。
そのため、共生型の立ち上げや制度に精通した専門家(コンサルタントなど)をつけた方がスムーズに事業を軌道に乗せられると思います。介護福祉だけでなく、障害福祉など他領域へサービスを広げることは、今後の福祉業界において非常に重要になるので、将来を見据えてぜひチャレンジしていただきたいです。