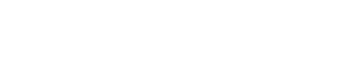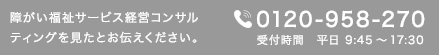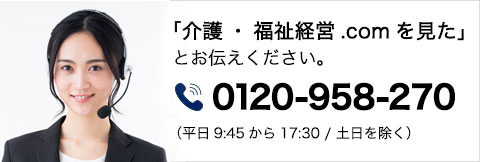全国でも稀有な成功事例に学ぶ!地域福祉を牽引する社会福祉法人豊明会さまに聞く「共生型デイサービス」の成功の秘訣
高齢者デイサービスの経営環境が厳しさを増すなか、通所系サービスの新しい形として注目集めているのが「共生型デイサービス」です。
全国的にもまだ取り組み事例が少ない共生型サービスにいち早く着手し、地域包括ケアの実現に向けて邁進されている社会福祉法人豊明会様に、株式会社船井総合研究所の介護経営コンサルタントが、その導入経緯から収益構造、そして成功の秘訣までを深く掘り下げて伺いました。
企業紹介
社会福祉法人豊明会は、宮城県栗原市を拠点に、高齢者福祉と障がい者支援の両分野で地域に根差したサービスを展開する総合福祉法人です。
特別養護老人ホームや共生型デイサービス、グループホーム、放課後等デイサービス、相談支援事業所など、多様な施設を通じて、子どもから高齢者まで幅広い世代が安心して暮らせる地域づくりを進めています。
法人理念である「豊かに明るい未来に向かって」のもと、職員一人ひとりが“相手を想う心”を大切にし、利用者の尊厳を守りながら自立を支える支援を実践しています。
また、地域包括支援センターの運営や送迎用福祉車両の導入など、地域社会とのつながりを意識した活動にも積極的に取り組んでいます。
豊明会は、「地域福祉への貢献、地域の皆様と共に、地域に求められるサービス」を提供し続けることで、地域の方々に愛され、必要とされる存在であり続けることを目指しています。
共生型デイサービスの成功の秘訣:Q&A形式
Q.全国的にもまだ事例の少ない共生型デイサービスを導入された背景、特に高齢者デイサービスから転換しようと考えられたきっかけは何だったのでしょうか。
A. 共生型サービスの検討は、平成28年頃から始まりました。
当法人はもともと高齢者と障がい者それぞれの事業を展開しており、それぞれの拠点に事業所を構えていました。
しかし、利用者様やご家族から「おじいさんは別の施設に行かなければならない」「障がいのある方はこっちの通所にいく」「利用時間や送迎時間が違うこと」「体調不良時はそれぞれを迎えに行く」といった、建物ごとにサービスが分かれていることに対するお声がけをいただくことが増えたのです。
特に、高齢者と障がい者が同じ家族にいる場合、サービス提供者が異なると「個別の契約が必要になること」「内容が同じでも福祉事業所別に説明を繰り返し行う必要があったり」、「サービス利用の利便性をより向上する必要がある」「障がい者福祉サービスから高齢者福祉サービスへのスムーズな移行も含む」多くの課題がありました。こうした課題、特に「5080問題」なども見据え、同じ建物でご家族皆様の支援ができないかという複合的な考え方を形にするため、共生型デイサービスを導入しました。
Q. 高齢者デイサービス専門の職員様が高齢者だけでなく、幅広い年齢層・特性を持つ障がい者の方々を受け入れる際、現場での戸惑いや直面した課題はありましたか。また、どのように乗り越えられましたか。
A. 職員の戸惑いはありました。
当法人では平成21年から障がい者事業を実施していたため、法人全体として障がい者支援に対する大きな課題にはありませんでしたが、介護保険事業を専門にやってきた職員にとっては、18歳から60代まで幅広い年齢層の方が利用されることへの戸惑いがありました。
これを解消するため、もともと障害福祉サービス、生活介護事業にいた専門スタッフを共生型の事業所に人事異動で配置し、専門的な知識を持ったスタッフがいる環境でスタートを切りました。
また、若く動きが活発な利用者様の支援に慣れていない職員に対しては、法人内の生活介護を見学する、体験するなどのスタッフが研修を組んでサポートを行いました。
さらに、障がいの特性として「音が苦手な方」や「周りの環境からシャットアウトして一人になりたい環境」を求める方もいらっしゃるため、個別ニーズに対応できるよう、事業所内にパーテーションをして区切れる場所を設け、個別の支援を確保する環境整備を行いました。
Q.収益面についてお伺いします。御社における共生型デイサービスの収益構造、特にメリットだと感じている点について教えてください。
A.まず、当法人は社会福祉法人という特性上、収益を最優先する考え方ではなく、地域のニーズに応えることを出発点としています。
しかし、事業を継続するためには当然収益は重要な為、 各事業所の強みを拡充し、続けることを目指しています。
共生型生活介護事業の収益的なメリットは、高齢者福祉、障がい者福祉の相互メリットを合わせることができる点です。
高齢デイサービスのメリットは1回の利用単価は高いことです。ですが、週2回、週3回という利用がスタンダードです。障がい者生活介護のメリットは「利用期間の長さ」と「利用頻度の高さ」にあります。
障がい者の方は利用期間が長く、中には20代から利用され、20年以上利用される方もおります。
また、生活介護は需給制度のため、に21日〜22日間支給されほぼ毎日来ていただけるため、介護保険の収益とは違ったメリットとなっております。
さらに、当法人ではグループホームを運営しており、共生型デイサービスを利用される方の多くがグループホームの入居者様でもあります。
日中、グループホームでもサービス提供は可能ですが、共生型サービスにて個別支援計画に基づいた自立支援サービスを提供することにより、個別の自立支援サービスの質、ご利用者のQOLを更に向上することを目指しており、結果的にグループホームの負担軽減となり、共生型サービスの強みである日中活動、自立支援に特化した支援が確立され、法人全体として収益が増につながっています。
単独での運営は厳しい可能性もありますが、複合的な組み合わせスケールメリットを活かした福祉事業として成立しています。
Q.共生型デイサービスはまだ認知度が低い地域も多いかと思います。営業戦略、特に利用者獲得のポイントについてお聞かせください。
A.共生型デイサービスを選んでいただく大きな理由は、サービスが「パッケージング」されていることにあります。
外部の方や計画相談事業所からお話をいただく際、「もう(サービスが)揃っているんですよね?」と聞かれます。
当法人は37年間培った事業とスケールメリットを活用し、送迎から食事、入浴といった日中の支援はもちろんのこと、当法人は計画相談事業所やグループホーム、短期入所事業も有しているため、「必要とされる限り年齢やサービス区分を問わずサービス提供を行う」というサービス提供体制を構築できます。
このことにより、ご家族にとっては、将来的に介護保険へ移行する際もスムーズに移行できることや、本人の特性や状況に合わせて法人内で多様なサービス(他の生活介護やグループホームなど)への組み換えができる「振り幅の大きさ」顔なじみのスタッフが繋ぎの役割を果たし、利用者の方のサービス区分が変わった際にはスムーズな移行が可能となり、継続利用のような安心感へとつながります。
また、ご紹介いただく際は自治体(特に福祉室や保健師)や、医療機関(医師、相談担当者)との結びつきを強くしています。
利用者様を「ください」と依頼するのではなく、「ご相談いただければ、うちにはこれだけのスタッフがいて、一緒に考えることができます」という姿勢で連携を深めています。
これにより、医療機関などから「こういうサービスが必要な方がいるが、どこでやっているか」と家族に聞かれた際に、当法人を紹介してもらえる機会につながります。
Q.最後に、これから共生型デイサービスへの転換を検討している、高齢者デイサービス経営者に向けたメッセージや、成功に向けたご助言をお願いいたします。
A.当法人としましても「ニーズが増えてきたのかな」という地域の声がきっかけでした。
しかし、共生型を始めたことによって、当法人の可能性、未来が大きく広がったのは間違いありません。
特に、地域の人口減少が進む地域の中で、高齢者だけ、障がい者だけという単一のサービスではなく、介護と障がいの「振り幅が大きいサービス」のニーズは今後ますます増えてくると感じています。
共生型は、多様なニーズを持つ利用者、地域の皆様に対し、インクルーシブ、誰しも包み込む」ような、地域包括ケアに不可欠な役割を担うサービスです。
既存の介護デイサービスの強み(特に身体介護や入浴支援など)は、他の生活介護事業所では強みとはしていないことが多く、共生型の大きなアドバンテージとなります。
まずは足元を見ながら、既存の資源(スケールメリット)をいかに組み合わせるかを考え、一歩一歩進んでいくことが着実な成長につながるサービスだと確信しています。