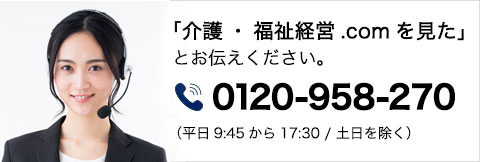訪問介護(ヘルパーステーション)良運営の事例

グローフォース生井代表に聞く – 訪問介護の運営と今後について
高齢化が進む現代において住み慣れた地域での生活を支える、訪問介護サービスはますますその重要性を増しています。しかし人材不足や報酬のマイナス改定、そして事業所倒産数の増加といった厳しい現実が業界を取り巻いています。
今回、私たちはグローフォースの生井代表に訪問介護事業の運営と今後についてお話を伺いました。
鍵を握るサービス提供責任者 – その成否は会社側の姿勢に
生井代表は訪問介護の運営において重要だと考えることの一つとして、サービス提供責任者(以下、サ責)の役割をあげました。「サ責の存在は非常に大きい。能力を十分に発揮できるか否かは他でもない会社側の姿勢にかかっている」とおっしゃいます。
運営において大切にしている「パートナーシップと信頼の構築」について、詳しくお話を伺いました。
1. サービス提供責任者の役割:「登録ヘルパー第一主義」と「パートナーシップの推進」
グローフォースにおいて、サ責は単なる業務管理者ではありません。現場で活躍する登録ヘルパーを中心に据え、彼らが働きやすい環境づくりに尽力します。『ありがとう』『大変だったね』といった共感の言葉を積極的にかけ、モチベーションの向上とチームの結束を重視しています」と生井代表。さらに現場からの意見や提案には迅速に対応し、課題解決に共に取り組むことでヘルパーとの信頼関係を深めています。
2. パート職員の役割:「サ責を支える縁の下の力持ち」
パート職員は利用者へのサービス提供はもちろんのこと、サ責のサポート役として事務作業の補助、関係機関との連携、電話応対など事業所の円滑な運営に不可欠な存在です。特に、利用者やその家族への丁寧な接遇は、サービスの質を高める上で重要な役割を担っています。
3. 会社の姿勢:「管理者を守る強固な支援体制」
グローフォースではサ責や管理者が孤立しないよう、支援体制を整えています。特にクレームや困難事例の対応について会社が前面に立ち弁護士や行政との連携も視野に入れ、スタッフの安心を最優先に行動しています。このような会社の姿勢が職員の自信と業務への集中を支えています。
4. 「一人ではない」と実感できる職場環境
訪問介護は一人で利用者の自宅を訪問するケースが多く、責任の重さから孤独を感じやすい職種です。しかしローフォースでは、サ責、パート職員、登録ヘルパー、そして会社全体が連携し支え合うことで、「一人ではない」と感じられる職場環境が醸成されています。この強い一体感こそが、質の高い訪問介護サービスを提供する原動力となっているのです。
人材育成と定着へのこだわり – “女子の気持ちがわかる責任者”
人材育成と定着への強いこだわりも、グローフォースの特徴の一つです。特にサ責には、ヘルパーの気持ちを丁寧に汲み取れる人物を求めています。「サ責は、ヘルパーの気持ちを理解し、細やかな気配りができる存在でなければなりません」と生井代表は強調します。
業務負担の大きいサ責をサポートするため、パートヘルパーを配置し、登録ヘルパーの窓口としての役割も担わせています。入社時の研修では、頻度の高い失敗事例を共有し、訪問介護における介護保険の理解を深めることに注力。未経験者には最大1ヶ月の同行研修を実施するなど、丁寧な育成体制を整えています。待遇面においても、ガソリン代は1サービス当たり一律200円を支給するなど、手厚いサポート体制を構築。「登録ヘルパー、職員ファーストの意識を責任者たちが持つことが大切です」という生井代表の言葉からは、現場で働く人々への思いやりが感じられます。
三位一体の連携が地域を支える
サービス提供責任者の献身的なリーダーシップ、パート職員の温かい支援力、そして会社の後方支援体制。この三位一体の連携こそが、グローフォースが地域で信頼される訪問介護サービスを提供し続ける土台となっています。
安定経営と質の高いケア – 特定事業所加算が示す信頼の証
グローフォースは、「特定事業所加算Ⅰ・Ⅱ」を取得しており、これは質の高いサービス提供の証となります。加算Ⅰの事業所は、売上高約500万円、利用者数95~100名、サ責3名体制という安定した経営基盤を築き、約20名の登録ヘルパーと6名のパートヘルパーが活躍しています。
また、加算Ⅱの事業所も、売上約250万円、利用者約60名、サ責2名体制(うちパート0.5名)、登録ヘルパー15名、パートヘルパー2名と、着実に運営されています。「加算Ⅰの取得は、安定経営に不可欠です」と生井代表は語り、利用者やその家族からの信頼が安定した事業運営を支えていることを示唆しました。
訪問介護の未来について – 制度改革への懸念と新たな可能性
訪問介護の未来について、生井代表は制度変更への懸念も示しています。特に、要介護1・2の生活援助が総合事業に移管される可能性については、「加算Ⅱの事業所の存続に関わる危機感を抱いています」と率直な思いを語りました。
一方で将来的には自社で訪問看護ステーション設立も視野に入れ、包括的な在宅ケアサービスの提供を目指すという新たな展望も示してくれました。「自分の両親は在宅で看取りたい」と語る生井代表の言葉には住み慣れた家で最期の時を迎えたいという普遍的な願いと、それを支えたいという強い思いが込められています。