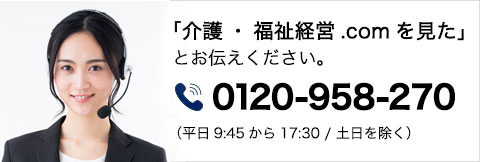住宅型/サ高住に定期巡回併設の成功事例
はじめに 高齢化が深刻化する日本において、住み慣れた地域で24時間安心して生活を送りたいというニーズはますます高まっています。そのニーズに応えるサービスとして、定期巡回随時対応型訪問介護看護は、「定額」で利用者様の状態や希望に合わせて、必要な時に必要なサービスを提供できるため、大きな注目を集めています。 しかしながら、定期巡回事業は、いまだ全国で1300事業所ほどしかなく、その中でも赤字経営に苦しむ事業所も少なくありません。事業を成功させるには、詳細な事業計画と収益性を担保できる戦略が不可欠です。 そこで今回は、定期巡回の成功事例として株式会社リビングプラットフォームの塩野介護事業部長に、船井総合研究所の介護経営コンサルタントが、定期巡回事業立ち上げの経緯から成功の秘訣、そして今後の展望まで、詳しくお話を伺いました。 今回ご紹介する「株式会社リビングプラットフォーム」は、「持続可能な社会保障制度の構築」をビジョンに掲げ、全国に介護・障がい者支援・保育を中心とした140以上の事業を展開している法人です。定期巡回事業に関しては、住宅型有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅に併設する形で、同法人で5事業所、子会社のブルー・ケア株式会社で3事業所の計7事業所を運営しています。今回は同法人の全国の事業所を担当されている塩野介護事業部長に取材しました。

介護事業部長 塩野 隆 様
Q&A
Q.船井総合研究所: 定期巡回サービスを開始した経緯を教えてください。
A.塩野様: 国が2012年4月から定期巡回・随時対応型訪問介護看護の制度を開始したことを受け、同年10月に札幌市東区でスタートしました。その経緯として、同時期に開設された住宅型有料老人ホーム「ライブラリ元町」がきっかけとなっています。通常であれば訪問介護でサービスを提供するところを、新たな試みとして定期巡回を導入することになりました。施設の開設と定期巡回サービスの開始が同時期であったことが、良いきっかけになったと思います。

サービス付き高齢者向け住宅「ライブラリ元町」
Q.船井総合研究所: 住宅型有料老人ホームの定期巡回併設において直面した課題はありましたか?
A.塩野様:訪問看護を併設したことで、医療依存度の高い方の新たな住まいとしての役割を期待していましたが、実際には軽度の方の利用が多かったようです。理由として地域のケアマネジャーの方々の認識として、「住宅型は軽度者向け」というイメージが根強かったため、重度者の受け入れが進みませんでした。札幌市内では、住宅型有料老人ホームは軽度者向けの施設という認識が一般的であり、ケアマネジャーの方々もシンプルな基準で判断する傾向がありました。そのため、訪問看護を併設していることのメリットが十分に伝わらず、当初想定していた事業所のあり方と少しずれが生じていました。
Q.船井総合研究所: その状況をどのように打開したのですか?
A.塩野様:訪問看護が併設されていることのメリットを、ケアマネジャーの方々に時間をかけて丁寧に説明しました。数年かけて徐々に理解が深まり、他社との差別化が浸透していきました。札幌市内では、定期巡回サービスの割合が低く、ケアマネジャーの方々の認知度も高くありませんでした。そのため、札幌市が主体となって、ケアマネジャー向けの勉強会が開催されるなど、地域全体での定期巡回への理解が深まったことも追い風となりました。数年かけて、ようやく「介護付き有料老人ホームに行かなくても、住宅型でも十分なサービスが受けられる」という認識が広まっていきました。
Q.船井総合研究所: 現在、定期巡回事業は全国で7ヶ所展開されていますが、運営形態はどのようになっていますか?
A.塩野様:北海道で5ヶ所、神奈川県相模原市で2ヶ所の計7ヶ所で定期巡回事業を展開しており、これらの事業所はすべて住宅型有料老人ホームまたはサービス付き高齢者向け住宅に併設する形で運営しています。子会社であるブルーケアでは、定期巡回に加え、利用者向けの通所介護も併設しています。定期巡回で必要なサービスを提供し、その上で残りの時間やサービスを通所介護で利用してもらうことで、利用者一人ひとりの状態やニーズに合わせた、きめ細やかなサービス提供を目指しています。
さらに、福祉用具の利用も組み合わせることで、利用者の生活の質(QOL)の向上を支援し、可能な限り自立した生活を送れるよう支援しています。
Q.船井総合研究所:定期巡回の収益面について教えてください。
A.塩野様:平均介護度2.5前後で、定期巡回単体で見たときの介護保険収入は1人あたり月12~13万円程度です。住宅型有料老人ホームのため、家賃や食費も別途いただいており、すべて合わせると1人あたりの平均単価は月30~40万円程度となっています。事業所ごとの入居定員数によって変わりますが、月商で見ると定期巡回のみの保険収入で1000万を少し超える収益となっています。なお、通所介護を併設している施設では、平均単価はもう少し高くなります。
Q.船井総合研究所: 従業員の方の人件費率はどのくらいですか?
A.塩野様:全体売上に対して、人件費率は4割前後で推移しています。具体的に札幌市にある事業所では、売上高が約2100万円に対し、人件費が約800万円と人件費率が38%程度に抑えられています。これらの事業所では、高い売上を維持しながら、効率的な人員配置を行うことで、収支差を担保できており、営業利益率は10~20%の間で推移しています。
Q.船井総合研究所: 訪問介護と比較して、定期巡回ならではの強みはありますか?
A.塩野様:定期巡回は「定額」でサービスを提供できるため、計画に基づいた柔軟な対応ができています。訪問介護と比べて、記録作業によるスタッフの精神的な負担も軽減されます。訪問介護では、サービス内容や時間によって単位数が変動するため、記録や報告が煩雑になりがちです。しかし、定期巡回では、月額の包括的な料金設定となっているため、サービス内容や時間にとらわれず、利用者様の状況に合わせて柔軟にサービスを提供できます。例えば、入浴介助が必要な日に体調が悪く、清拭のみで済ませた場合でも、訪問介護のような単位数の変更は発生しません。また、サービス提供時間についても、厳密な時間管理が求められないため、スタッフは時間に追われることなく、利用者様とのコミュニケーションを重視したサービスを提供できています。
Q.船井総合研究所:訪問人材の採用でお困りの企業様が多いですが、採用で工夫している点はありますか?
A.塩野様:弊社では法人全体で毎月100名程度の採用ができています。具体的な方法としては、ハローワークやindeedなどの求人媒体を活用し、地域の相場よりも高い給与を設定することで、応募数を増やしています。介護業界は人材不足が深刻化しており、人材獲得競争が激化しています。そのため、求職者にとって魅力的な条件を提示することが重要であると考えています。地域における給与水準を常に把握し、それよりも高い給与を設定することで、求職者の関心を引いています。高い給与を提示できるような、収益性の高い事業を立ち上げるという、会社の事業戦略が、一番の工夫かもしれません。
また、有料掲載を細かく管理することで、求職者への露出を高めています。有料掲載では、地域や職種、雇用形態など、様々な条件でターゲットを絞り込むことができます。これらの機能を活用し、最適なターゲットに求人情報を配信することで、採用効果を高めています。他にも特定技能制度も活用し、外国人人材の採用も積極的に行っています。特定技能制度とは、一定の技能を持つ外国人を日本で受け入れるための制度です。この制度を活用し、ミャンマーやインドネシアなど、複数の国から外国人人材を採用しており、常勤職員の10%にまで進んでいます。
Q.船井総合研究所: 定期巡回の職員で苦労する点はありますか?
A.塩野様:まず、入社してはじめての職場が定期巡回の場合、定期巡回の働き方がスタンダードになるため、抵抗感は少ないようです。次に、他の事業からの異動者についてですが、その場合も抵抗感は少ない傾向があります。
介護付き有料老人ホームからの異動者にとっては、身体的な負担が少ないと感じるようですし、訪問介護からの異動者にとっては、記録業務の負担が少ないと感じるようです。訪問介護の経験者からは、「定期巡回の方が気持ち的に楽だ」という声も聞かれます。訪問介護では、サービス内容や時間によって細かく記録する必要があり、イレギュラーな対応も多いため、煩雑な事務作業に起因する精神的な負担が大きいと感じる方もいます。しかし、定期巡回では、包括的な料金設定となっているため、サービス内容や時間にとらわれず、利用者様の状況に合わせて柔軟に対応できます。そのため、精神的な負担が軽減され、利用者様と向き合う心の余裕が生まれ、働きやすいと感じるスタッフが多いようです。
Q.船井総合研究所:今後の定期巡回事業の展望について教えてください。
A.塩野様:今後も医療依存度の高い方でも住宅型で安心して生活ができるようにしていきたいと思っています。そのため、介護福祉士の割合を高め、特定事業所加算の取得を目指すなど、サービスの質を向上させるとともに、加算による収益性の強化も目指していきたいと思います。また、今後は医療ニーズの高い利用者様の受け入れを強化するため、訪問看護ステーションとの連携をさらに深めていきたいと考えています。具体的には、医療依存度の高い方や、終末期の方への対応を強化し、住宅型有料老人ホームでも安心して最期まで過ごせる体制を構築していきたいと考えています。医療保険対応の訪問介護を中心としたメディカルサービスを提供する子会社として2024年11月に「メディカルプラットフォーム」を新たに設立し、医療連携をさらに強化していく方針です。